こんにちは、福祉イノベーションズ大学の いっちー教授です!💡
今日は、社会福祉士国家試験対策にピッタリなテーマをお届けします。
その名も… 「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の違い!🎯
「この言葉、どこかで見たことあるけど、実際どういう意味なの?」「試験対策として押さえておくべきポイントって?」
そんな疑問をお持ちのあなたに、 めちゃくちゃわかりやすく 解説しちゃいますよ!🔥
この記事では、 基本的な概念の説明 から、 試験対策として押さえるべきポイント まで、一緒に学んでいきます。
例題を交えながら進めていくので、「試験に出たら自信を持って答えられる!」状態を目指しましょう!✨
それでは、授業スタートです!📚
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
内発的動機づけと外発的動機づけの基本🚀

まずは「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」について、基礎からしっかり理解していきましょう!
この2つの概念をしっかり押さえることが、国家試験対策のカギになりますよ。
「内発的」とか「外発的」と聞くと、「なんだか難しそう…」と感じる方もいるかもしれませんが、大丈夫!
具体例を交えながら、 小学生でもわかるレベル で説明していきますね!🌈
内発的動機づけとは?✨
内発的動機づけ は、簡単に言うと、
「自分がやりたい!」と思う気持ちで行動すること を指します。
例えば…
- 絵を描くのが楽しくて、つい夢中になっちゃう🎨
- 本を読むのが好きで、時間を忘れて読書する📚
これらは、 外から報酬をもらえるわけでもなく、自分自身が楽しいからやる行動 ですよね?
これが 内発的動機づけ のポイントなんです!
💡 ポイント
- やりたい気持ちの源は自分の中 にある!
- 外からの報酬や評価に関係なく、「楽しい」「好き」という気持ちが原動力になる!
重要キーワード は「楽しさ」「自己満足」。これを覚えておけばOKです!👍
外発的動機づけとは?✨
一方、外発的動機づけ は、
「外からの報酬や評価が目的」で行動すること を指します。
例えば…
- 宿題をやったらご褒美にアイスをもらえる🍦
- 良い成績を取ったら、お小遣いが増える💰
これらの行動は、 外からの報酬 (アイスやお小遣い)が目的になっていますよね?
これが 外発的動機づけ の特徴です!
💡 ポイント
- やりたい気持ちの源は外部から!
- 報酬や評価、場合によっては罰を避けるために行動する!
重要キーワード は「報酬」「評価」「外部の影響」。ここが内発的動機づけとの大きな違いです!🌟
ここまでのまとめ
- 内発的動機づけ → 楽しくて、自分からやりたい!
- 外発的動機づけ → 報酬や評価が欲しくてやる!
次は、この違いを実際の試験問題で確認してみましょう!🎯
📚 児童福祉法の基礎知識を深め、試験対策を強化したい方は、こちらの記事も参考にしてください:

基本問題で理解を深める💡

「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の違いはわかったけど、実際の試験ではどう出題されるの?🤔
ここでは、具体的な問題を通じて理解を深めていきます!
試験に出る可能性大の内容なので、しっかりチェックしてくださいね!✏️
設問と正解の解説📝
では、まずは以下の設問を見てみましょう!
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 人前で楽器を演奏することが楽しくて、駅前での演奏活動を毎週続けた。これは、内発的動機づけによる行動である。
- お小遣いをもらえることが嬉しくて、玄関の掃除を毎日行った。これは、内発的動機づけによる行動である。
- 出席するたびにシールをもらえることが楽しくて、ラジオ体操に毎日通った。これは、内発的動機づけによる行動である。
- 絵を書くことが楽しくて、時間を忘れて取り組んだ。これは、外発的動機づけによる行動である。
- 成功すれば課長に昇進できると言われ、熱心に仕事に取り組んだ。これは、内発的動機づけによる行動である。
答え)1. 人前で楽器を演奏することが楽しくて、駅前での演奏活動を毎週続けた。これは、内発的動機づけによる行動である。
正解は 「1」 です!🎉
内発的動機づけの具体例と解説🎨
まず、選択肢の「1」を見てみましょう。
1. 人前で楽器を演奏することが楽しくて、駅前での演奏活動を毎週続けた。
この行動のポイントは…
- 楽器を演奏すること自体が楽しい!
- 外部からお金や物をもらうわけではない!
このように、「楽しい」「好き」という気持ちで行動しているので、これは 内発的動機づけ の典型例です!💡
重要!
内発的動機づけは、 外部の報酬や評価に影響されず、自分自身の中から湧き出る楽しさや満足感 がカギになります!
外発的動機づけの具体例と解説💰
次に、選択肢の「2」と「3」を見てみましょう。
2. お小遣いをもらえることが嬉しくて、玄関の掃除を毎日行った。
この行動では、お小遣い という外部からの報酬が行動の目的になっていますね。
つまり、これは 外発的動機づけ です!
3. 出席するたびにシールをもらえることが楽しくて、ラジオ体操に毎日通った。
同じく、ここでも シール という外部からの報酬がポイント。
これも 外発的動機づけ に該当します!
重要!
外発的動機づけは、 外からの報酬や評価が行動の原動力 になっていることを押さえておきましょう!
次は「4」と「5」の選択肢について詳しく解説します!
内発的動機づけのもう一つの具体例🖌️
続いて、選択肢「4」を見てみましょう!
4. 絵を書くことが楽しくて、時間を忘れて取り組んだ。
この行動のポイントは…
- 外からの報酬や評価が目的ではない!
- 自分自身が楽しいから、つい時間を忘れて取り組んでしまう!
つまり、これは 内発的動機づけ による行動です。
わかりやすい例え✨
例えば、友達と一緒にお絵描きをしていたら、「あれ?もう夕方⁉」なんて経験ありませんか?
楽しくて時間を忘れるような行動は、まさに 内発的動機づけ の象徴です!🎨
外発的動機づけの具体例としての昇進目標💼
最後に、選択肢「5」を見てみましょう。
5. 成功すれば課長に昇進できると言われ、熱心に仕事に取り組んだ。
この行動のポイントは…
- 昇進という 外部の報酬 が目的!
- 昇進することがなければ、同じように頑張らない可能性が高い!
このように、 外部からの報酬や評価がモチベーション となっているので、これは 外発的動機づけ に該当します!
わかりやすい例え✨
「テストで100点取れたらゲーム買ってあげるよ!」と言われて、一生懸命勉強する子どもがいたら、それは 外発的動機づけ です!💰
問題のまとめとおさらい📝

今回の問題を通して、次のポイントをしっかり押さえましょう!
- 内発的動機づけ → 楽しくて、自分の意思でやる行動!
- 例:「絵を書くのが楽しいから時間を忘れて没頭する」
- 外発的動機づけ → 報酬や評価を目的にした行動!
- 例:「昇進のために頑張って仕事をする」
試験問題では、この違いを見極める力が問われます!✨
覚え方はとってもシンプル。「楽しさ=内発的」「報酬=外発的」 と考えればOKです!
次は、内発的動機づけと外発的動機づけの 実際の使い分け について解説します!💡
内発的動機づけと外発的動機づけの使い分け🛠️

ここからは、 内発的動機づけ と 外発的動機づけ を実際にどう使い分けるのかを解説します!
「どんな場面でどっちを意識すればいいの?」という疑問を解消しちゃいましょう!
この理解が深まると、試験問題だけでなく、 社会福祉の現場でも役立つ知識 になるので、しっかり押さえていきましょうね!✨
それぞれが発揮されやすい場面とは?🌟
内発的動機づけが活きる場面🎨
内発的動機づけ は、次のような場面で力を発揮します!
- 趣味や好きなことをしている時
- 例:絵を描くのが楽しくて、つい夢中になっちゃう🎨
- 自分で考えた目標に向かって頑張る時
- 例:好きな本を読んで知識を深める📚
こうした場面では、 「自分が楽しいからやる」 という気持ちが原動力になります。
だから、 人が自発的に動ける環境 を作るのが重要なんですね!
💡 福祉現場の具体例
例えば、高齢者施設でのレクリエーション活動。
参加者が「楽しい!」と思える内容(例:好きな音楽やゲーム)を提供することで、内発的動機づけを引き出せます!🎵
外発的動機づけが効果的な場面💰
一方で、外発的動機づけ は、次のような場面で効果を発揮します!
- 報酬や評価がはっきりしている時
- 例:会社で成果を出すと昇進やボーナスがもらえる💼
- 新しい行動を始める時
- 例:「運動を続けたら特典がもらえるよ!」といったきっかけ作り🏅
特に 行動を始めるきっかけ として、外発的動機づけはとても有効です。
ただし、報酬がなくなるとやる気も低下することがあるので、長続きさせる工夫が必要です!
💡 福祉現場の具体例
子ども支援の場で、ラジオ体操を促す際に「出席カードにスタンプを押す」といった仕組みを用意すると、外発的動機づけが働きます!✨
内発的動機づけと外発的動機づけを組み合わせよう🔗
実際の現場では、 内発的動機づけ と 外発的動機づけ を組み合わせて使うのが効果的です!
例えば…
- 最初は外発的動機づけで行動を始めてもらい、徐々に内発的動機づけに移行させる
- 例:ラジオ体操を続けることで「体が軽くなった!」という喜びを感じてもらう🌈
このように、 外発的なきっかけを活かしつつ、内発的な楽しさや意義を見つけてもらう のが理想の形です!
次は、社会福祉士国家試験における 内発的動機づけ・外発的動機づけの重要性 について解説します!💼
社会福祉士国家試験対策としての重要性📘

内発的動機づけと外発的動機づけは、社会福祉士国家試験において 頻出のテーマ です!
「どちらの動機づけに当てはまるか?」を問う問題がよく出題されるので、違いをしっかり理解しておきましょう!
また、試験対策だけでなく、福祉現場でも知識を応用できるため、学ぶ価値は大きいですよ!✨
試験で問われやすいポイント🎯
1. 具体例から動機づけの種類を判断する問題
試験では、具体的なエピソードが提示され、それが 内発的動機づけ か 外発的動機づけ かを判断する問題がよく出ます。
例題
- 「〇〇をすることが楽しくて続けている」 → 内発的動機づけ
- 「〇〇をしたらご褒美がもらえるから続けている」 → 外発的動機づけ
ポイントは、 行動の原動力が自分の中にあるか、外部にあるかを見極めること です!
2. 福祉現場における活用方法を問う問題
もう一つの出題傾向は、 内発的・外発的動機づけを福祉の現場でどう活かすか に関する問題です。
例題
- 「利用者が自発的に参加したいと思う環境を作る」 → 内発的動機づけを促す取り組み
- 「報酬や評価を提示して行動を促す」 → 外発的動機づけを利用する取り組み
このように、福祉現場での実践を意識した出題も多いので、現場の具体例をイメージしながら学ぶと覚えやすいですよ!
過去問の傾向と対策📊
過去問を分析すると、以下のような傾向があります!
- 選択肢に細かい設定がある問題が多い
→ 一つ一つの選択肢をじっくり読んで、行動の動機を正確に見極めることが重要です! - 具体例が現場を連想しやすい内容
→ 高齢者支援、児童支援、就労支援など、福祉の現場でのシチュエーションが出題されることが多いです!
対策ポイント
- 日常的な行動例に置き換えて考える
- 「この行動は、自分が楽しんでやっているのか、それとも報酬を目指しているのか?」と具体例をイメージして考えましょう!
- 過去問を繰り返し解く
- 問題パターンに慣れることが、合格への近道です!
次は、これまでの内容を わかりやすくまとめ ていきます!✨
まとめ🌟

今日のテーマである 「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」 について、重要なポイントをおさらいしましょう!
内発的動機づけとは?✨
- 定義:自分自身が楽しい、やりたいと感じる気持ちで行動すること
- キーワード:楽しい、自己満足、好き
- 例:絵を描くのが楽しくて、時間を忘れて取り組む
💡 試験での押さえどころ
「行動の原動力が自分の中にある場合は内発的!」と覚えましょう!
外発的動機づけとは?✨
- 定義:外部からの報酬や評価が目的で行動すること
- キーワード:報酬、評価、外部からの影響
- 例:昇進するために仕事を頑張る
💡 試験での押さえどころ
「行動の理由が外部の報酬なら外発的!」と考えると簡単に判断できます!
試験対策のポイント📘
- 問題文をじっくり読んで、行動の動機を判断することがカギ!
- 「行動の理由が自分の楽しさか、外部からの報酬か」を見極めましょう!
- 具体例を頭に入れておくと判断がスムーズ!
福祉現場での活用方法🔧
- 内発的動機づけ:利用者が楽しく取り組める環境を作ることが重要!
- 例:高齢者施設でのレクリエーション活動
- 外発的動機づけ:行動を始めるきっかけ作りに有効!
- 例:ラジオ体操への参加を促すためにスタンプカードを活用
最後に💬
内発的動機づけと外発的動機づけの違いを理解することで、試験対策もバッチリ!
さらに、福祉の現場での実践にも役立つ知識なので、ぜひ覚えておきましょう!
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
<この記事のQ&A>📝

Q1. 内発的動機づけと外発的動機づけの違いは何ですか?
A1. 内発的動機づけは「自分の楽しさや満足感」が行動の原動力となるものです。
例:絵を描くのが楽しくて夢中になる。
外発的動機づけは「外部からの報酬や評価」が目的となるものです。
例:昇進やご褒美のために頑張る。
Q2. 福祉現場で内発的動機づけを引き出すにはどうしたら良いですか?
A2. 利用者が自分の意思で「やりたい!」と思えるような環境を作ることが大切です。
例:利用者の好きな音楽や活動を取り入れることで、楽しみながら参加できる環境を提供する。
Q3. 外発的動機づけはどんな場面で有効ですか?
A3. 外発的動機づけは、行動を始めるきっかけ作りに有効です。
例:ラジオ体操に出席するたびにスタンプを押す仕組みを作ることで、継続する意欲を引き出す。
Q4. 試験対策として覚えておくべきポイントは?
A4. 行動の理由を見極めることが重要です!
- 「自分が楽しくてやっている」→ 内発的動機づけ
- 「報酬や評価が目的になっている」→ 外発的動機づけ
過去問を繰り返し解くことで、判断基準が身につきます!
Q5. 内発的動機づけと外発的動機づけを組み合わせることはできますか?
A5. できます!
外発的動機づけで行動を始めてもらい、徐々に内発的動機づけに移行させる方法が効果的です。
例:スタンプカードで運動を始めてもらい、運動の楽しさを実感してもらう。

















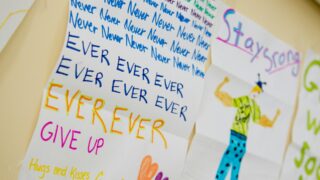



コメント