みなさん、こんにちは!福祉イノベーションズ大学のいっちー教授です!✨
今回は、1973年に行われた「老人医療費の無料化」について、めちゃくちゃテンション高めで解説していきます!📚💪
1973年、日本は高齢者を対象に「医療費を無料にする」という政策を始めました。この画期的な取り組みがどんな影響を与えたのか、一緒に見ていきましょう!
「なんで無料にしたの?」「どんな問題が起きたの?」という疑問もバッチリ解決します!🌟
この記事を読めば、高齢者福祉や医療制度についての理解が深まり、社会福祉士国家試験にも役立つ内容をゲットできますよ!それでは早速始めましょう!🎈
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
📚 福祉三法・六法・八法の成り立ちや歴史を詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください:

老人医療費の無料化とは 🏥✨

1973年、日本では70歳以上の高齢者を対象に医療費の自己負担をなくすという政策がスタートしました!この政策は「老人福祉法」の改正をきっかけに実現したんです。では、どうしてこんな政策が必要だったのでしょうか?
制度の概要と背景 📜
1970年代の日本は、高齢者人口が急激に増え始めていました。それに伴って、病気やケガで医療が必要な高齢者も増加。でも、当時は高額な医療費が家計の大きな負担となり、「病院に行きたくても行けない」という人がたくさんいました。
そこで国は、高齢者の健康を支えるために「70歳以上の医療費は無料にしよう!」という大胆な政策を実施。これにより、すべての70歳以上の高齢者(寝たきりの場合は65歳以上)が、病院での診察や治療を自己負担なしで受けられるようになったんです!🎉
実施された経緯 🌟
実は、この政策の前にいくつかの自治体が「老人医療費無料化」を試験的に始めていました。例えば、東京都と秋田県が1969年に導入し、「これ、全国でやったらどうなる?」と注目されたんです。
その結果、1973年に全国で制度化されました。特に戦後の経済成長を背景に、「国全体で高齢者を支えよう!」という雰囲気があったことも、実現の後押しになったんですね!💪
📚 日本と世界の福祉制度の歴史を深く学びたい方は、こちらの記事も参考にしてください:

老人医療費の無料化がもたらした影響 🧐

では、医療費が無料になることで、どんな影響があったのか見ていきましょう!ここからが本題です!🔥
社会的入院の増加 🏨
医療費が無料になったことで、病院の利用が増加しました。その結果、家族が高齢者を福祉施設ではなく病院に長期入院させる「社会的入院」という現象が広がります。
社会的入院とは?
病気やケガではなく、介護や生活のために病院に長く入院することを指します。たとえば、「親を福祉施設に入れると世間から非難されそう…」という理由で、病院を選ぶ家族が増えたんですね。
これによって、病院が高齢者でいっぱいになり、本来必要な医療が受けられなくなるケースも出てきました。
社会的入院が引き起こした問題 ⚠️

老人医療費の無料化によって広がった「社会的入院」ですが、これがもたらした問題も多かったんです。ここでは具体的にどんな影響があったのかを掘り下げていきます!🔍
廃用症候群の発生とその要因 💊
病院に長期間入院していると、心身の機能が低下してしまうことがあります。これを「廃用症候群」といいます。たとえば、一日中ベッドで寝ているだけだと筋力が落ちたり、歩けなくなったりしますよね。
また、「関節が硬くなる(関節拘縮)」「床ずれ(褥瘡)」など、介護が必要な状態がさらに悪化することも…。こうした現象が高齢者の長期入院で多発しました。
例え話でイメージしよう!
たとえば、小学生が夏休みにずーっとソファでゴロゴロしてたら、足が鈍くなって運動会で走れなくなる…。それと似た現象が高齢者に起きていたんです!
過剰医療と出来高払い制度の問題 🏥💸
もう一つの問題は「過剰医療」です。当時の病院は、患者に行った治療や投薬の回数に応じて収益が増える「出来高払い制度」を採用していました。
その結果、
- 薬を多めに処方する
- 必要以上に検査をする
といった「薬漬け」や「検査漬け」が広がってしまいました。これは患者の健康を害するだけでなく、医療費の無駄遣いにもつながりました。
現代に続く社会的入院の課題 🚑

「過去の話でしょ?」と思った方もいるかもしれませんが、実は社会的入院の問題は今も完全には解決されていません。では、現在の課題を見ていきましょう!
家族の選択肢の狭さと過剰な医療依存 🛏️
現代の高齢者やその家族は、必ずしも望んでいない医療や入院を余儀なくされることがあります。例えば、
- 胃瘻(いろう):口から食べられない高齢者にチューブで栄養を入れる処置
- 精神病院への長期入院:認知症の高齢者が退院できない状態
これらは、医療技術の進歩と引き換えに生じた新たな問題です。患者本人や家族の意思が尊重されにくい状況が今も残っています。
老人医療費政策の教訓とこれからの展望 🌍✨

1973年の老人医療費無料化政策は、その時代の背景やニーズに応えるための画期的な試みでした。しかし、その一方で予想外の問題も引き起こしました。この経験から、どんな教訓を得られるのでしょうか?また、未来の高齢化社会にどんな施策が求められるのでしょうか?
1973年の政策の評価 🔍
老人医療費無料化政策は、高齢者の医療アクセスを大幅に改善したという点で非常に意義深いものでした。「お金がないから病院に行けない」という不安を取り除き、多くの高齢者が医療を受けられるようになったんです。
ただし、
- 病院に依存しすぎたケア体制
- 医療費の急増による財政圧迫
といった課題も同時に生じました。国民全体で支える仕組みを考える必要性が、この時代から顕著になったんです。
高齢化社会に向けた福祉政策の今後 💡
現在の日本は、1973年のころ以上に超高齢化社会となっています。これに対応するためには、次のような取り組みが重要になります。
- 地域包括ケアシステムの充実
- 高齢者が病院に依存せず、地域で安心して暮らせる仕組みを整える。
- 具体例:在宅医療や訪問介護サービスの普及。
- 家族負担の軽減
- 家族だけで高齢者を支えるのではなく、社会全体でサポートする体制を作る。
- 具体例:介護保険制度の充実、柔軟な働き方の導入。
- 医療費の適正化
- 無駄な医療を減らし、必要なケアに集中する仕組み作り。
- 具体例:医療と福祉の連携、過剰医療の見直し。
まとめ 🌟

1973年の老人医療費無料化は、高齢者福祉の歴史における大きな一歩でした。その経験を活かしながら、現代の超高齢化社会に対応するための新しい仕組みを構築する必要があります。
「支え合う社会」を実現するために、私たち一人ひとりが福祉や医療の課題に関心を持つことが大切です!✨
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
<この記事のQ&A> 💡

Q1. 老人医療費無料化の対象者は誰でしたか?
A1. 対象者は、70歳以上の高齢者(寝たきりの場合は65歳以上)でした。この政策により、高齢者の医療費自己負担がなくなり、病院での診察や治療を無料で受けられるようになりました。
Q2. 社会的入院とは何ですか?
A2. 社会的入院とは、病気やケガが直接の理由ではなく、生活のために病院に長期入院することを指します。これは、「老人福祉施設に入所するのは避けたい」という当時の社会的風潮が背景にあります。
Q3. 廃用症候群とは何ですか?
A3. 廃用症候群とは、長期間ベッドで過ごすなど、体を動かさない状態が続くことで起こる心身の障害です。具体例として、筋力の低下、歩行困難、関節拘縮、褥瘡(床ずれ)などがあります。
Q4. なぜ過剰医療が問題になったのですか?
A4. 当時の病院は「出来高払い制度」を採用しており、治療や検査の回数に応じて収益が増える仕組みでした。このため、不必要に薬や検査が増える「薬漬け」「検査漬け」が問題視されました。
Q5. 現代に求められる高齢者福祉の課題は何ですか?
A5. 主に以下の3つが挙げられます:
- 地域包括ケアシステムの充実(地域で支える仕組み)
- 家族負担の軽減(社会全体でのサポート)
- 医療費の適正化(無駄を省き必要なケアを提供)




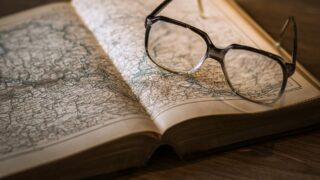














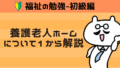

コメント