こんにちは!福祉イノベーションズ大学のいっちー教授です!👨🏫✨
みなさん、社会福祉士の国家試験対策、進んでいますか?試験範囲が広くて「どこに力を入れていいか分からない…」って思うこと、ありますよね!😰
でも大丈夫!今回は超重要テーマである福祉事務所について、テンション爆上げで解説しちゃいます!🎊
この記事を読めば、福祉事務所の仕組みや役割、配置される職員の要件までバッチリ理解できますよ!
さらに、試験に頻出の「社会福祉主事」のポイントも分かりやすくカバー。**社会福祉士を目指すみなさんの”心強い味方”**になる内容をお届けします!💪✨
では早速、福祉事務所の世界へ冒険スタート!🏰🚀
福祉事務所とは?🧐

**福祉事務所って名前は知ってるけど、具体的にどんな場所かイメージできない…**っていう人も多いはず!
簡単に言うと、福祉事務所は地域の「福祉のなんでも相談窓口」です。👩⚕️💼
例えば、こんな感じで考えてみてください!
- 困っている人の支援をする場所
→ 生活保護や子育て支援、高齢者の相談など、幅広い福祉サービスを提供します! - 都道府県や市町村に必ずある施設
→ 都道府県には絶対に設置が義務付けられていて、市町村も設置する場合が多いです。ただし、小さな町村ではないこともあります!
**「あれ、都道府県と市町村で違いがあるの?」**と思ったあなた!💡そこが試験でも重要ポイントなんです!次で詳しく解説しますよ~!
福祉事務所の設置のルール!📜

福祉事務所がどこに設置されるかは、法律でしっかり決められています。これ、試験でもめちゃくちゃ出やすいですよ!😲
- 都道府県の場合:全47都道府県に設置義務あり!
→ 絶対に1つ以上は設置されています。お住まいの県庁所在地には必ず福祉事務所がありますよ! - 市町村の場合:設置義務は市だけ!
→ 市には必ず福祉事務所が設置されますが、町や村では任意です。
例えば…
「人口1,000人の小さな村」だと福祉事務所がないこともあります。その場合、近くの市の福祉事務所が対応するんですね!🏘️
まとめポイント!
市町村=「設置義務あり」が市、任意が町村!これを覚えましょう!📖✨
生活保護だけじゃない!福祉事務所の役割🛠️

「福祉事務所って、生活保護だけやってる場所?」と思ったあなた!違います!😲
実は、福祉事務所はとっても多機能な施設なんです!
都道府県と市町村で少し役割が違いますが、それぞれが管轄する法律があります。ここ、試験に出やすいので要注意!⚡
- 都道府県福祉事務所の役割
→ 管轄するのは「福祉三法」
生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法の業務を主に行います。 - 市町村福祉事務所の役割
→ なんと「福祉六法」を扱います!
福祉三法+知的障害者福祉法・身体障害者福祉法・老人福祉法が追加され、対応範囲が広がります!
「福祉六法が多いのはなぜ?」
これには歴史的背景があります!1990年以降、市町村の福祉機能が強化され、管轄業務が移譲されたからなんですね。📜✨
福祉事務所に配置される職員の役割✨

福祉事務所は、ただの建物じゃありません!中には専門知識を持った職員たちが配置され、重要な役割を担っています。💼🌟
では、どんな職員がいて、どんな仕事をしているのか見ていきましょう!
所長(リーダー的存在!)🕴️
福祉事務所には必ず所長がいます!
所長は、福祉事務所の運営を総括する責任者。指導や監督を行い、全体を取りまとめます。
例えるなら…?
学校でいえば校長先生のような存在ですね!所長がしっかりしていないと、福祉事務所全体がスムーズに動かないんです。🏫
指導監督を行う職員(社会福祉主事)📋
この職員が、福祉事務所での相談業務や現場の指導を行います。
条件として「社会福祉主事」でなければなりません!
ここでポイント!
- 社会福祉主事とは、特別な資格ではなく任用資格です。
- 任用資格とは?
「その役職に就いた時点で資格を得る仕組み」のこと。例えば、社会福祉士の資格を持っている人が福祉事務所に採用されれば、その時点で社会福祉主事になります。
具体例でイメージ!
たとえば、あなたが「社会福祉士」として採用され、福祉事務所で働くことになりました。その瞬間、あなたは自動的に社会福祉主事としての役割を担うわけです!📌
ケースワーカー(現業員)🏡
ケースワーカーは、生活保護の支援や相談者の家庭を訪問するなど、現場で活躍する職員です!
この役割も、社会福祉主事の任用資格が必要です。
わかりやすい例
例えば、困っている家庭に訪問して「どんなサポートが必要か」を一緒に考えたり、生活が立て直せるようアドバイスをしたりするお仕事です!
事務職員(縁の下の力持ち!)📠
福祉事務所の事務作業を担う職員。申請の受付や記録作成などを行います。
この職員は社会福祉主事でなくてもOK!
気になる年齢制限!🕒
現在、社会福祉主事になるには「20歳以上」であることが必要です。ただし、2022年以降、成人年齢の引き下げに伴い18歳以上になると予想されています。
大切なポイント!
試験で「社会福祉主事は25歳以上でなければならない」などの引っかけが出たら要注意!現在は20歳以上ですから、しっかり覚えておきましょう!🔔
社会福祉主事とは?📖✨

「社会福祉主事」って、福祉事務所の重要な役職だけど、どうやったらなれるの?と思った方!
ここで、社会福祉主事について徹底解説していきます!💡
社会福祉主事になる条件🔑
特別な試験は必要ありません!
社会福祉主事は、以下のいずれかの条件を満たせばOKです!
- 社会福祉士の資格を持っていること
→ 社会福祉士資格があれば、自動的に社会福祉主事の資格もゲット! - 大学で指定科目を履修して卒業すること
→ 厚生労働大臣が指定した福祉科目を3科目以上修めればOKです!
具体例でわかりやすく!
例えば、「福祉政策論」「社会福祉法」「児童福祉論」などの科目を大学で学び、単位を取るだけで条件クリアです!🎓 - 指定養成機関を修了すること
→ 都道府県知事が指定した養成機関で必要な課程を修了すれば、社会福祉主事になれます!
社会福祉士と社会福祉主事の違い❓
試験資格 vs. 任用資格
- 社会福祉士:国家試験に合格して取得する「資格」です!
- 社会福祉主事:福祉事務所などで働くための「任用資格」です!
簡単に覚えるコツ!
- 社会福祉士:「自分が資格を持っている」
- 社会福祉主事:「職場で任されて資格が生まれる」
社会福祉主事の特徴🏆
社会福祉主事は、地域の福祉を支える「縁の下の力持ち」。特に、福祉事務所では必須の存在です!
たとえば、福祉サービスが必要な人の相談に乗り、解決に向けて具体的な支援プランを考える役割を担います。
重要!試験対策ポイント!
- 社会福祉主事は「補助機関」である!
→ つまり、市長や知事が決めた業務をサポートする役割を持っています。
社会福祉士国家試験対策で押さえるべきポイント🔥

福祉事務所や社会福祉主事に関する問題は、試験の頻出テーマです!重要なポイントをまとめます!
試験頻出テーマ① 補助機関 vs. 協力機関の違い
- 補助機関:社会福祉主事
→ 福祉事務所の業務をサポート! - 協力機関:民生委員
→ 地域のボランティアとして福祉を支援!
覚え方のヒント!
補助=「職場の中でのサポート」
協力=「地域全体でのサポート」
試験頻出テーマ② 過去問を活用する!📚
過去問では「社会福祉主事になる条件」や「福祉事務所の管轄業務」がよく出題されています。具体的にはこんな感じ!
例題:社会福祉主事になる条件に該当しないものを選べ!
→ 「社会福祉士の資格を取得していない」や「指定科目を履修していない」が引っかけで出ることが多いです!
福祉事務所に関する頻出問題を攻略!🚀

国家試験対策では、福祉事務所に関連した具体的な法律や歴史的背景が問われることが多いです。
ここでは、試験に出やすいトピックをさらに深掘りしていきます!📖✨
福祉事務所の設置に関する法律📜
福祉事務所の設置や運営は、社会福祉法に基づいています。この法律では、福祉事務所の基本的な役割や組織構成が明確に定められています。
試験で狙われるポイント!
- 福祉事務所は「社会福祉法」に規定されている!
→ 生活保護法など、個別の福祉法ではありません!
具体例
「福祉事務所の設置基準は、生活保護法で定められている」という選択肢が出たらバツ!😵✖️
正解は、社会福祉法に基づいていると答えましょう!
管轄業務の変更の歴史🏛️
試験では、法律の改正や管轄権限の変更に関する歴史が問われることもあります。以下の流れを覚えておくと便利です!
- 1990年:進退障害者福祉法・老人福祉法が改正され、入所措置権限が都道府県から市町村へ移譲!
- 2003年:知的障害者福祉法でも同様に入所措置権限が市町村へ!
これらの改正によって、市町村福祉事務所が「福祉六法」を管轄することになりました!📜✨
社会福祉主事と民生委員の役割の違い🤔
試験では、「社会福祉主事は補助機関」「民生委員は協力機関」という区別が頻出です!
ポイントまとめ
- 社会福祉主事:補助機関 → 市長や知事の指示をサポートする役割
- 民生委員:協力機関 → 地域の住民と連携して支援する役割
数字や条件に注意!🔢
試験では、「年齢」「義務か任意か」といった数字や条件がよく狙われます!
例えば…
- 社会福祉主事になるには現在は20歳以上!(将来的には18歳以上)
- 福祉事務所の設置義務は都道府県と市だけ!(町村は任意)
これらをしっかり押さえれば、試験の正答率がグッと上がりますよ!📈✨
まとめ🎉
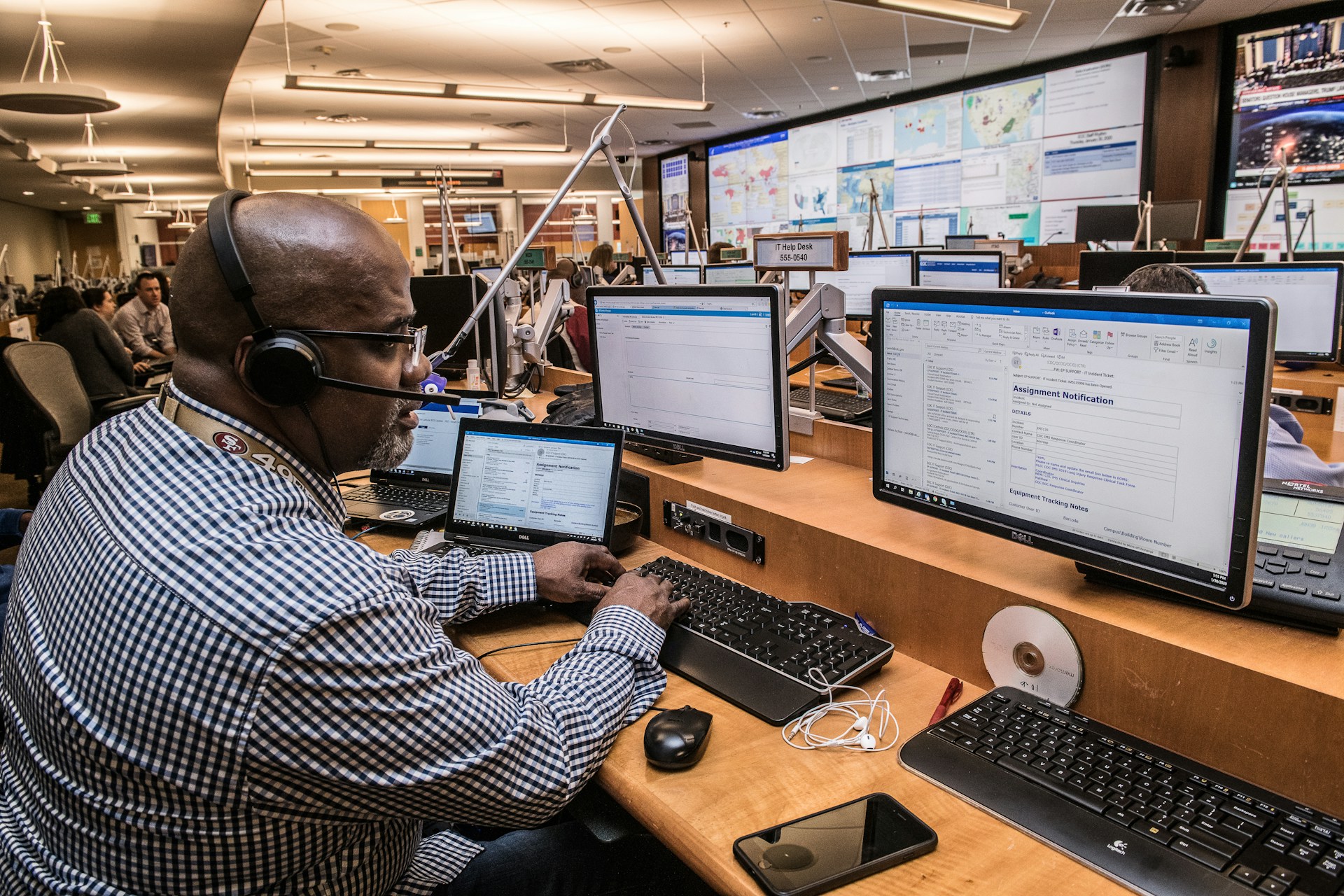
福祉事務所や社会福祉主事について理解を深めることで、国家試験の対策が一歩進みます!✨
この記事の内容を繰り返し復習して、合格に向けて自信をつけていきましょう!💪🎓
<この記事のQ&A>🎓💡

Q1. 福祉事務所の設置義務があるのはどこですか?
A1. 都道府県と市に設置義務があります。町村は任意設置なので、場合によっては設置されていないこともあります。
Q2. 都道府県福祉事務所と市町村福祉事務所の管轄業務の違いは何ですか?
A2. 都道府県福祉事務所は「福祉三法(生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法)」を管轄します。
市町村福祉事務所は、これに加えて「知的障害者福祉法・身体障害者福祉法・老人福祉法」を含む「福祉六法」を管轄します!
Q3. 社会福祉主事と社会福祉士の違いは何ですか?
A3. 社会福祉主事は任用資格であり、特定の条件を満たせば資格を得られます。一方、社会福祉士は国家試験に合格して取得する資格です。
Q4. 福祉事務所でケースワーカーになるための条件は?
A4. ケースワーカーは、社会福祉主事であることが条件です。社会福祉士資格がある方や大学で指定科目を履修した方が任用されることが多いです。
Q5. 社会福祉主事の最低年齢は何歳ですか?
A5. 現在は20歳以上が条件ですが、2022年以降は成人年齢引き下げに伴い18歳以上に変更される見込みです。
Q6. 試験でよく出る「補助機関」と「協力機関」の違いは何ですか?
A6. 補助機関は「社会福祉主事」で、行政をサポートする役割です。協力機関は「民生委員」で、地域住民との連携が主な役割です。















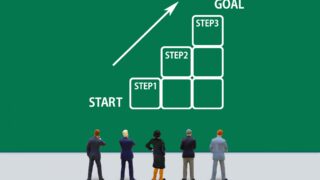




コメント