こんにちは、みなさん!福祉イノベーションズ大学のいっちー教授です!👨🏫✨
今日も一緒に社会福祉士国家試験の合格を目指して、楽しく学んでいきましょう!💪🎯
今回のテーマはズバリ、「障害者基本法の重要ポイント」についてです!🎉
この法律、聞いたことはあるけれど、内容を具体的に説明しろと言われると「あれ?🤔」となる方も多いのではないでしょうか?
でも大丈夫!この記事を読めば、障害者基本法の基本から試験頻出の改正点まで、スッキリ理解できますよ!🌟
さらに、最後には模擬問題で確認しながら理解を深められる構成になっています!📝💡
それではさっそく、楽しい授業を始めていきましょう!😄✨
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
📚 障害者基本法の成り立ちや関連する福祉三法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください:

障害者基本法の基本を理解しよう!🌈
![]()
障害者基本法は、日本の法律の中でも障害者にとって特に大切なものなんです!📜
「障害者」と聞くと、どんなイメージがありますか?🤔 実はこの法律、障害者に関する権利や支援の基盤となる法律なんですよ!
「えっ、基盤って何?」と思った方のために説明すると、基盤とは「家でいう土台」みたいなものです🏠。家がしっかり立つには土台が必要ですよね?同じように、障害者に関する他の法律や制度も、この障害者基本法をもとに作られているんです!✨
障害者基本法の目的と意義を解説するよ!🌟
障害者基本法の目的は、ズバリ「障害者が社会で安心して暮らせるようにすること」です!🌍💖
障害者も健常者も関係なく、みんなが同じように生活できる社会を目指しています。これを「共生社会」って呼びますよ!🎉
たとえば、段差がある階段しかない建物があったら、車いすの人はどうでしょう?上がれなくて困りますよね?😥
そこで、スロープやエレベーターをつけることによって、障害のある人でも安心して利用できるようにする!これが障害者基本法の理念なんです!🚪✨
この法律がなかったら、たくさんの人が困ってしまいます。でも、障害者基本法のおかげで、社会全体が「みんなにやさしい設計」を考えるようになってきました。これって素敵なことですよね?💖
障害者の定義とは?ポイントを整理しよう!📚✨

さて、まずは「障害者の定義」について詳しく見ていきましょう!👀
障害者基本法では、障害者について次のように定義されています:
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(第2条第1号)。
これをもっと簡単に言うと、障害や社会的な壁のせいで、普段の生活がずっと困難な人を指します!
「一時的なケガ」は障害者に含まれる?🤔
たとえば、「階段から落ちて足を捻挫しちゃった人」はどうでしょう?一見すると、車いすが必要で不便そうですよね。でも、これは一時的なものです!⏳
障害者基本法では、「継続的に」生活に困難がある人が対象なので、こういった「一時的なケガ」は含まれません!💡
例えるなら、風邪を引いて熱が出ている状態を「病気」と言いますが、風邪が治れば健康になりますよね。同じように、障害者基本法では、一時的な状態は「障害」に含まれないんです!😊
ポイントを押さえよう!🔑
障害者の定義を覚えるためのポイントは、「継続的に困難」というキーワード!これを押さえておけば、試験でも安心です!👌✨
また、選択肢に「一時的に歩行困難になった者も障害者に含まれる」と書いてあったら、これは間違いです!試験では、こういったひっかけ問題も出るので注意してくださいね!⚠️
📚 社会保障制度の歴史や重要な改革について詳しく学びたい方は、こちらの記事も参考にしてください:

試験頻出!障害者基本法の改正点を解説!📖🌟

次に、障害者基本法の中でも特に試験に出やすい「改正点」を押さえましょう!✨
障害者基本法は、時代に合わせて内容が変わってきました。その中でも、2011年の改正はとても重要です!🎯
社会的障壁の追加とその背景🛠️
2011年の改正で新しく追加されたのが「社会的障壁」という考え方です!💡
社会的障壁とは、「障害がある人が、生活する上で障害になる社会の仕組みや慣習」を指します!
例えば…
- 車いすの人が入れない段差の多い建物🏢
- 障害者のことを考えずに作られた制度📋
- 偏見や差別のある考え方💭
これらが「社会的障壁」です!障害そのものだけでなく、社会の側にある「壁」を取り除こう!という考え方が、2011年に新しく盛り込まれました。
これによって、障害者にやさしいデザインや制度がどんどん増えてきています。これも、障害者基本法の大きな進化のひとつなんですよ!✨
自立への努力規定の削除とその意義📝✨

もうひとつ重要な改正ポイントとして、「自立への努力」という文言の削除があります。
実は、2004年以前の障害者基本法には、次のような規定がありました:
「障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない」
一見すると、「頑張って社会に参加しようね!」と言っているように思えますよね?💪
でも、この文言は問題視されることになりました。なぜでしょうか?
「努力を求める」のは適切か?🤔
障害者にとって、日常生活そのものがすでに大変な場合も多いんです。
それなのに、「もっと頑張れ!」と努力を求めることは、不公平に感じる人もいました。
例えば、視力が極端に低い人に「ちゃんと文字を読めるように努力しなさい!」と言うのは無理がありますよね。📚
だからこそ、「努力を義務づける文言は適切ではない」という考え方が広まり、2004年にこの規定が削除されました。✂️✨
削除の意義🌈
この改正によって、障害者基本法は「障害者に頑張らせる法律」ではなく、「障害者を社会全体で支える法律」へと進化しました!
たとえば、「みんなで助け合う」という考え方を広げ、段差のない道を作ったり、手話通訳者を増やしたりする取り組みが進んでいます。これって素晴らしい進歩だと思いませんか?👏💖
試験では、「現在も自立への努力が規定されている」といったひっかけ問題が出ることがあります。なので、この改正点をしっかり押さえておきましょう!✨
障害者基本法に規定されていない内容に注意⚠️
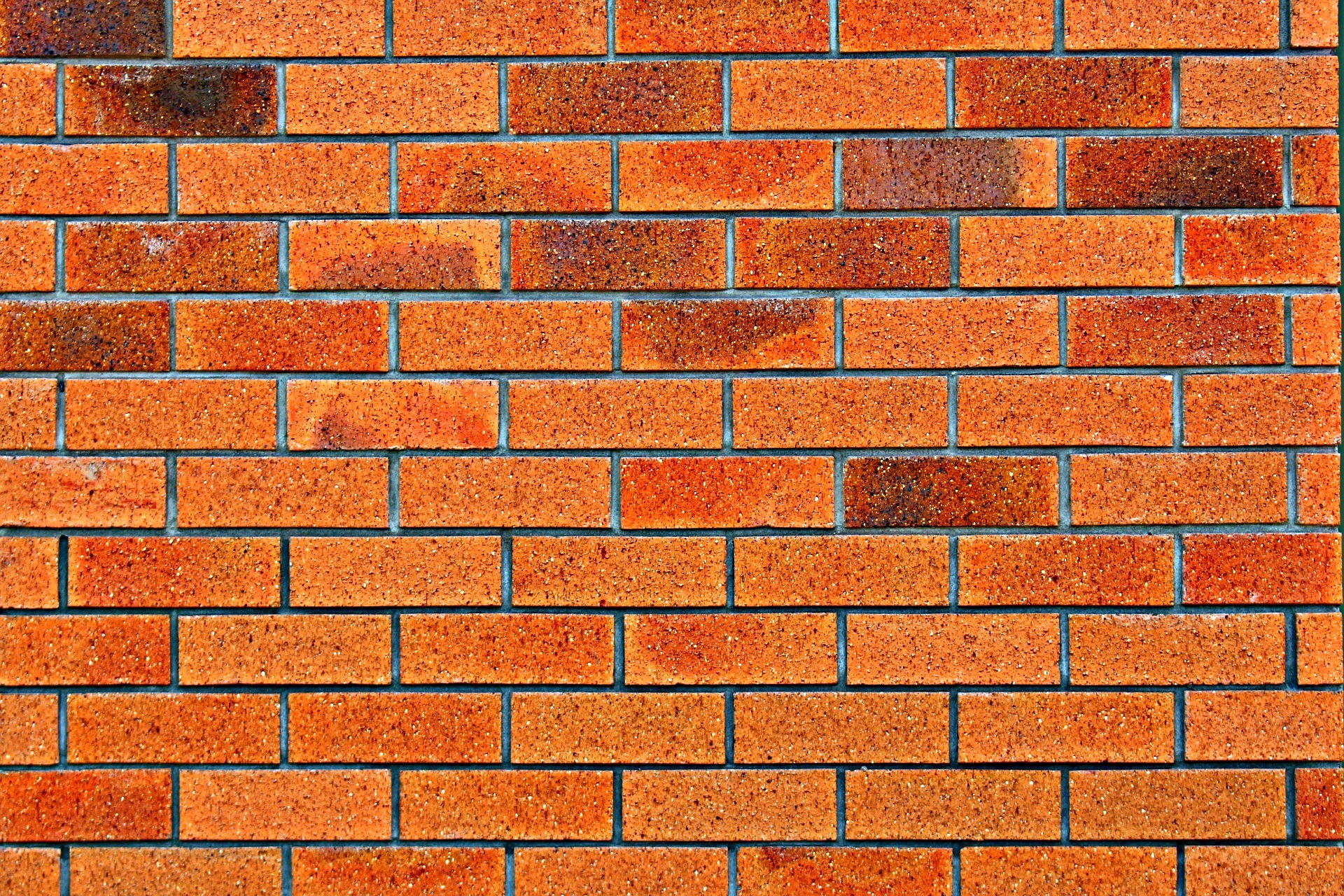
次に、試験でよく問われる「障害者基本法に規定されていない内容」について解説します!
障害者基本法はとても広い範囲をカバーしていますが、実は一部の内容は他の法律に規定されているんです。💡
地域生活支援事業の根拠法を知ろう!🏠
例えば、「市町村が行う地域生活支援事業」。これは、障害者にとって重要な支援ですが、障害者基本法には直接書かれていません!😲
この事業の根拠法は、「障害者総合支援法」です!
障害者総合支援法ってどんな法律?🤔
障害者総合支援法は、障害のある人が住み慣れた地域で生活するための具体的な支援を定めた法律です。💖
たとえば、こんな支援があります:
- 訪問介護(ヘルパーさんが家を訪れてお手伝いする)🏡
- 通所施設(リハビリや作業訓練を受けられる場所)🏢
- 移動支援(外出がスムーズにできるようにサポート)🚕
これらの支援を市町村が行うのは、障害者総合支援法に基づいているからなんです!✨
障害者政策委員会と名称変更の経緯をチェック!📜✨

次に押さえておきたいポイントは、「障害者政策委員会」についてです!
試験では、ここもひっかけ問題が出やすい箇所なので、しっかり確認しましょう!🧐
中央心身障害者対策協議会って何?🤔
昔は、現在の「障害者政策委員会」に当たる組織を「中央心身障害者対策協議会」と呼んでいました。
この名前、少しややこしいですよね…💦
でも、名前が変わっただけではありません!内容もより良いものに進化しています!🌟
名前が変わった理由と背景🌈
この組織の名称が変更されたのは、2011年の障害者基本法の改正のときです。
理由は、旧名称が「心身障害者」という言葉を含んでいたからなんです。
「心身障害者」という表現は、一部の障害者のみに焦点を当てた言い方に見えるため、より包括的な表現が求められました。そこで新しく「障害者政策委員会」という名前が採用されました!✨
試験でひっかからないためのポイント⚠️
試験では、今でも「中央心身障害者対策協議会」という旧名称で出題されることがあります!
でも、現在の法律では「障害者政策委員会」が正しいので、しっかり覚えておきましょう!✍️✨
障害者基本法と関連法の違いを理解しよう!🧐
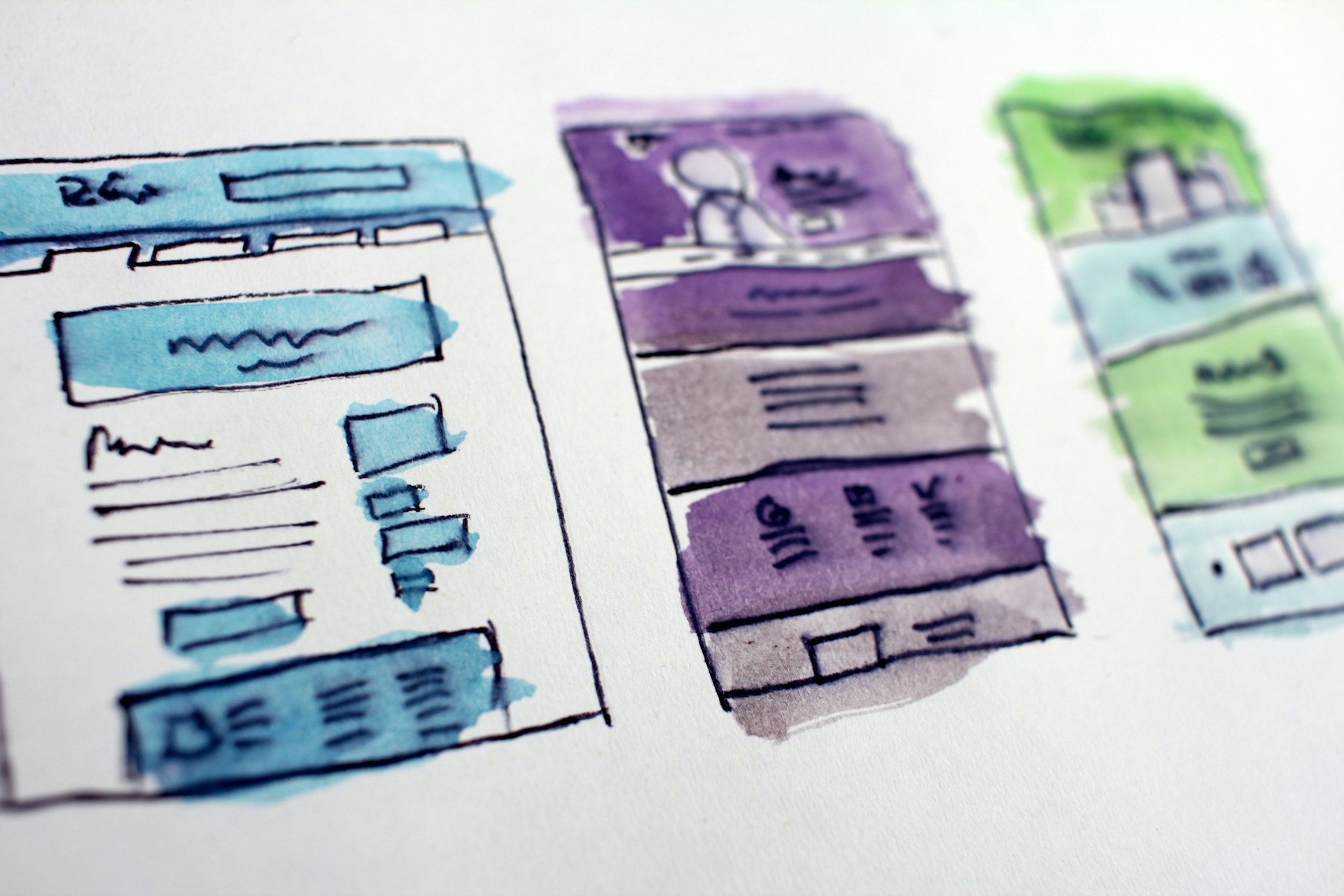
障害者基本法を正しく理解するためには、関連法との違いを知ることも重要です!
ここでは「障害者総合支援法」と「障害者差別解消法」という2つの関連法を取り上げて、わかりやすく解説します!🌟
障害者総合支援法との違い🏡
障害者総合支援法は、障害者が地域で生活するための具体的なサービスを規定しています。
さっき説明した「地域生活支援事業」もこの法律の一部です!
簡単に言うと…
- 障害者基本法:全体の方針を示す
- 障害者総合支援法:具体的な支援内容を規定する
という違いがあります!
障害者差別解消法とのつながり🤝
一方、障害者差別解消法は、「障害を理由にした差別をなくそう!」という法律です!💡
例えば…
- 視覚障害のある人が資料を読めるように、点字や音声対応を準備する📖🔊
- 車いすの人が利用できる店舗の設計を考える🏢
これらの取り組みは、障害者差別解消法によって推進されています!
障害者基本法が「大きな土台」だとしたら、差別解消法は「人との関わり方を改善するルール」と考えるとわかりやすいですね!✨
問題を通じて理解を深めよう!📝✨

さあ、最後は模擬問題を解きながら、これまでの学びを定着させましょう!💪
障害者基本法について、試験では次のような問題がよく出題されます。挑戦してみてくださいね!🎯
模擬問題:障害者基本法の基礎知識💡
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。
- 障害者基本法では、社会的障壁の除去について規定されている。
- 障害者基本法では、中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。
- 障害者基本法では、市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。
- 障害者基本法では、心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。
答え:2. 障害者基本法では、社会的障壁の除去について規定されている。
解説付き!間違いやすいポイント🤔
選択肢1:障害者の定義
障害者基本法における「障害者」は、「継続的に日常生活または社会生活に制限を受ける状態」であることがポイント!一時的なケガは含まれません。
選択肢3:障害者政策委員会
旧名称の「中央心身障害者対策協議会」は現在使用されておらず、「障害者政策委員会」が正しいです!
選択肢4:地域生活支援事業
この事業の根拠法は「障害者総合支援法」です!障害者基本法ではありません!
選択肢5:自立への努力
この文言は2004年に削除されています!「今も規定されている」という選択肢があったら注意です!⚠️
ポイントまとめ📚✨
試験で迷ったときは、次の3つを思い出してください:
- 障害者の定義=継続的な制限がある人
- 社会的障壁の除去が大切!
- 他の法律との違いを押さえること!
これを頭に入れておけば、障害者基本法の問題は怖くありません!😊✨
まとめ:障害者基本法を攻略して試験合格を目指そう!🎉

この記事では、障害者基本法の重要ポイントを楽しく学びました!🎯
障害者の定義や社会的障壁、改正点、関連法との違いなど、試験で問われる内容をしっかり押さえましたね!📖
障害者基本法は、ただ暗記するだけではなく、「なぜこの法律が必要なのか?」を理解することが大切です。これをきっかけに、さらに深く学んでいきましょう!🌟
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
<この記事のQ&A>🎓✨
Q1. 障害者基本法で定義される「障害者」とは誰のことを指しますか?
A1. 障害者基本法で定義される「障害者」とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)など心身の機能の障害があり、障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に制限を受ける状態にある人」のことを指します。一時的な状態やケガは含まれません。
Q2. 社会的障壁とは何ですか?
A2. 社会的障壁とは、「障害者の日常生活や社会生活を営む上で障害となる事物、制度、慣習、考え方などを指すもの」です。例えば、段差のある建物や偏見・差別が挙げられます。この概念は2011年の改正で新たに追加されました。
Q3. 自立への努力についての文言は今も規定されていますか?
A3. いいえ、規定されていません。「自立への努力」という文言は2004年の改正で削除されました。障害者自身に努力を義務づけるのではなく、社会全体で支えるという方向性に変わったからです。
Q4. 地域生活支援事業の根拠法は障害者基本法ですか?
A4. いいえ、地域生活支援事業の根拠法は障害者総合支援法です。この事業は市町村が実施するもので、訪問介護や移動支援など、障害者が地域で安心して生活するための具体的な支援内容が含まれています。
Q5. 現在の障害者基本法では「中央心身障害者対策協議会」が規定されていますか?
A5. いいえ、規定されていません。現在は「障害者政策委員会」が正しい名称です。旧名称で出題されることもあるので注意が必要です。

















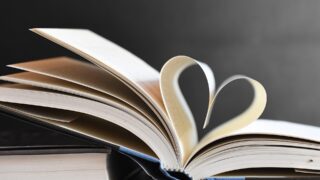

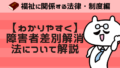
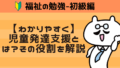
コメント