こんにちは~!🙌 いっちー教授です!
今日は、介護保険制度について一緒に楽しく学んでいきましょう!🧠✨
「介護保険って何?」「介護報酬ってどう決まるの?」なんて疑問を持っている方も多いはず!
この記事では、社会福祉士国家試験でも頻出の「介護保険制度」と「介護報酬」について、わかりやすく&楽しく解説していきます。🌟
これを読めば、介護保険制度の基礎はもちろん、試験に出るポイントまでバッチリ抑えられますよ!💯
それでは、さっそく授業を始めましょう~!📚✨
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
介護保険制度の基本を学ぼう🧓👴

みなさん、「介護保険制度」って聞いたことありますか?🤔
介護保険制度は、簡単に言うと、介護が必要な人たちを支えるためにみんなで助け合う仕組みなんです!
たとえば…
「年を取って体が弱くなってきた…」「認知症で日常生活が難しい…」そんなときに介護サービスを受けられる制度が、この介護保険なんです!💡✨
そして、この制度を運営しているのが、市町村(東京23区を含む)なんですよ!🏙️
では次に、具体的な仕組みについて見ていきましょう!👇
介護保険制度とは何か?その目的と仕組み🔍
介護保険制度の目的はズバリ!
「高齢者や介護が必要な方が住み慣れた地域で安心して生活を送れるようにすること」です!✨
この制度の仕組みは、みんなでお金を出し合って、必要なときにサービスを受けられるようにする「保険」という考え方がベースになっています。
例えば…
- みんなでお金を出し合う → 毎月、給料から介護保険料を納める!
- サービスが必要になったら申請! → 役所に「介護が必要です」と届け出ます!
- 審査を受ける → 本当に介護が必要かどうか専門家がチェック!
- OKが出たらサービスを利用できる! 🎉
こんな感じで、自分が大変なときに助けてもらえる仕組みなんですね!
保険者は市町村!介護保険制度の運営主体とは👩⚖️🏢
「保険者」というのは、介護保険を運営する役割を担う存在のことです!
介護保険制度では、保険者は全国の市町村と東京23区になります。
例えば…
「東京都渋谷区に住んでいるAさん」は、渋谷区が保険者になります。
「大阪市北区に住んでいるBさん」は、大阪市が保険者になります。
これらの市町村が、皆さんから集めた保険料や税金をもとに、介護保険制度を運営しているんです!✨
介護保険法における負担割合を理解しよう💰🤔
![]()
次に、介護保険制度を支えるお金の仕組みについて見ていきましょう!💡
「誰がどれくらい負担しているのか?」を理解すると、介護保険制度の全体像がもっと見えてきますよ!✨
「居宅給付費」と「施設給付費」の違いとは?🏠🏢
まず、介護保険法では、大きく分けて2つの給付費があります。
- 居宅給付費:自宅で介護サービスを受ける場合
- 施設給付費:介護施設(特別養護老人ホームなど)でサービスを受ける場合
たとえば、Aさんが自宅で訪問介護を受けるとしたら、「居宅給付費」が使われます。
一方、Bさんが特養(特別養護老人ホーム)に入所した場合は、「施設給付費」が使われるというわけです!
この違いを知っておくと、試験の選択肢を選ぶときに役立ちますよ~!🌟
国と地方自治体の負担割合をわかりやすく解説📝✨
さて、ここからが試験でも超重要ポイント!🎯
介護保険の財源を支える「国」と「地方自治体」が、どれくらい負担しているのかを見ていきます!
居宅給付費の場合
居宅(自宅)でサービスを受ける場合、国と地方自治体の負担割合は次のとおりです👇
- 国:25%(4分の1)
- 都道府県:12.5%(8分の1)
- 市町村:12.5%(8分の1)
つまり、国と地方自治体で1対1の割合になっているんです!
施設給付費の場合
一方で、施設でサービスを受ける場合はちょっと違います!👇
- 国:20%
- 都道府県:17.5%
- 市町村:12.5%
合計すると、国と地方自治体で2対3の割合になります!
わかりやすい例で説明👀
たとえば…
- Aさんが自宅で訪問介護を受けた場合、介護給付費の50%は公費(国と地方自治体)でまかなわれます。
- Bさんが施設に入所して介護サービスを受けた場合、地方自治体(都道府県と市町村)の負担割合が国より多くなります!
試験では、「居宅給付費は1対1、施設給付費は2対3」という違いが問われることがよくあります!
ここ、絶対に押さえておきましょう!🔥
介護保険の財源と都道府県の負担割合🗾💸

介護保険制度を運営するには、当然ながらお金が必要です!
ここでは、その財源の仕組みと、都道府県がどれくらい負担しているのかを解説します!✨
「1/4」と「1/8」の違いを理解しよう🧐
まず、介護保険制度の財源は、ざっくり分けるとこんな感じになっています👇
- 保険料:50%(利用者や被保険者が支払う)
- 公費:50%(国や地方自治体が負担する)
このうち、地方自治体が負担する割合には「1/4(25%)」や「1/8(12.5%)」という数字がよく出てきますが、これを正しく理解することが大事です!🔑
居宅給付費の場合🏠
居宅給付費では、都道府県は12.5%(8分の1)を負担します。
「1/4=25%」ではなく、都道府県の負担は「1/8=12.5%」という点がポイント!💡
たとえば…
- 国:25%(4分の1)
- 都道府県:12.5%(8分の1)
- 市町村:12.5%(8分の1)
このように、それぞれがバランスよく負担しているんです!
施設給付費の場合🏢
一方で、施設給付費では、都道府県が負担する割合は17.5%になります。
これは、居宅給付費よりも負担が多くなる点が特徴です。
たとえば…
- 国:20%
- 都道府県:17.5%
- 市町村:12.5%
これらを覚えておけば、試験で出題されても迷わず答えられますよ~!🎯
都道府県の負担割合を覚えるコツ📝✨
ポイントは、「8分の1=12.5%」と「17.5%」の違いです!
簡単に覚えるコツ👇
- 居宅=8分の1(12.5%)
- 施設=少し多めの17.5%
さらに、「介護保険の公費負担の内訳」も押さえておけばバッチリです!💪
しっかり覚えておきましょうね~!
📚 介護報酬の特徴を理解するために、介護業界の人材不足と若者の活躍について知ることも有益です。詳しくはこちらの記事をご覧ください:
介護報酬の特徴を押さえよう📊✨

次に、介護保険制度の大切な要素である介護報酬について学んでいきましょう!
「介護報酬ってどうやって決まるの?」「地域による違いはあるの?」といった疑問を、具体例を交えながら解説します!🌟
介護報酬は原則3年に1回改定される📆
まず、介護報酬がどれくらいの頻度で改定されるかを知っておきましょう!
介護報酬は、原則3年に1回改定されます。
ここで間違いやすいのが、「診療報酬(医療保険の報酬)」との混同です!😱
- 介護報酬:3年に1回
- 診療報酬:2年に1回
この違い、超重要ポイントです!🎯
なぜ3年に1回なの?🤔
介護報酬は、高齢者の数や介護の実態を考慮して見直されます。
例えば、
「高齢者が増えて、施設の利用が増えた」
「介護職員の人手不足が深刻化している」
こういった状況を反映して、報酬が適切になるよう調整しているんです!
介護報酬の単位制とは?地域による割増の仕組み🏙️
介護報酬は「単位制」という仕組みで決められています。
これ、少し難しく感じるかもしれませんが、具体例で見てみましょう!💡
単位制とは?
介護報酬は、サービスごとに「○○単位」という形で計算されます。
例えば、
- 訪問介護サービス:1回で約200単位
- デイサービス:1日で約500単位
ここでの「単位」は、基本的に1単位=10円が目安となります。
つまり、訪問介護1回(200単位)なら、200×10=2,000円が報酬になります!
地域による割増ってなに?
実は、この「1単位=10円」は全国一律ではないんです!
なぜなら、地域ごとに物価や生活費が違うから!🌍✨
例えば…
- 都会の方が物価が高い→割増あり!
- 地方は物価が低め→割増なし!
具体的には、1.4%~14%の範囲で割増率が設定されています。
具体例で見てみよう👀
たとえば、東京23区にある介護施設の場合…
1単位=10.5円(+5%割増)となることも!
一方で、地方の施設では、1単位=10円のままということもあります。
割増の理由は?🤔
なぜ割増が必要なのか、わかりやすく例えます!✨
例:都会と地方で魚を買う場合🐟
- 都会で魚を買う → 漁港から遠いので、輸送費や人件費がかかる!結果、高くなる!
- 港町で魚を買う → 近くで獲れるので、輸送費がほぼかからない!結果、安い!
介護報酬もこれと同じ仕組み!
都会では物価が高い分、介護職員のお給料を適切に支払うために報酬を割増しする必要があるんです!💡
介護保険制度を正しく理解して高齢者支援に役立てよう🙌🌟

ここまで、「介護保険制度」と「介護報酬」について解説してきました!
では最後に、試験に出やすいポイントを振り返りつつ、どのように学びを活かしていくかを考えていきましょう!✨
試験頻出!介護保険制度のポイントまとめ🎯
社会福祉士国家試験では、「介護保険制度」に関する問題が頻出です!
ここで押さえておくべき重要ポイントをもう一度おさらいしましょう!📝
1. 保険者は誰?
保険者は、市町村と東京23区です!
これを間違えると、試験で点数を落としてしまうので注意!💡
2. 負担割合の違い
- 居宅給付費:国と地方自治体が「1対1」
- 施設給付費:国と地方自治体が「2対3」
3. 財源の内訳
- 保険料50%、公費50%
- 都道府県の負担は居宅給付費で「1/8=12.5%」、施設給付費で「17.5%」
4. 介護報酬の改定頻度
介護報酬は、原則3年に1回改定されます!
診療報酬(医療保険)は2年に1回なので混同しないようにしましょう!
5. 介護報酬の単位制
- 基本は「1単位=10円」
- 地域によって割増率が「1.4%~14%」で異なる
これらのポイントを押さえておけば、試験でしっかり得点できますよ!🎉
介護報酬と制度の背景を押さえて活用する💪
介護保険制度は、高齢者や介護が必要な方が安心して暮らせるように作られた大切な仕組みです。
そして、それを支えるのが介護職員や私たち支援者の存在!🌟
実際に活用する場面でのポイント
- 利用者の状況を理解する
- 「この人にとって必要なサービスは何だろう?」と考える。
- 制度を正しく説明する
- 「保険料の仕組みやサービス内容を利用者さんに伝える」ことが大事!
- 介護職員の労働環境も考慮する
- 報酬が適切に配分されることで、介護の質が保たれる!
✨ お疲れさまでした! ✨
今回の記事で、介護保険制度と介護報酬についてバッチリ理解できましたね!
これらの知識を活かして、高齢者支援の現場や試験対策に役立ててください!💯
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
<この記事のQ&A>💡✨

Q1. 介護保険制度の保険者は誰ですか?
A1. 保険者は、全国の市町村と東京23区です!
Q2. 居宅給付費と施設給付費の違いは何ですか?
A2. 居宅給付費は、自宅で介護サービスを利用する場合の費用。
施設給付費は、特養などの施設で介護サービスを利用する場合の費用です!
Q3. 負担割合の違いはどう覚えればいいですか?
A3.
- 居宅給付費:国と地方自治体=1対1(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)
- 施設給付費:国と地方自治体=2対3(国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%)
「居宅は均等」「施設は地方多め」で覚えると簡単です!
Q4. 介護報酬の改定は何年に1回ですか?
A4. 介護報酬は、3年に1回改定されます。医療保険の診療報酬(2年に1回)と混同しないように注意しましょう!
Q5. 介護報酬の単位は全国一律ですか?
A5. いいえ、地域によって異なります!物価の違いを考慮して、1.4%~14%の割増が行われる仕組みになっています!



















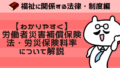

コメント