こんにちは~!✨
福祉イノベーションズ大学のいっちー教授です!😊
今日のテーマは 「開かれた質問」と「閉ざされた質問」の違い について!🎯 社会福祉士国家試験でもよく出題される超重要テーマなので、ここでしっかり理解を深めていきましょう!🔥
質問の仕方次第で、相手から得られる情報の質がガラッと変わること、知ってましたか?🤔✨ 「たかが質問」と侮るなかれ! 効果的な質問 を投げかけられるかどうかで、利用者さんとの信頼関係やコミュニケーションの深さが決まります!
さあ、この記事を読み終えた頃には「開かれた質問」と「閉ざされた質問」の違いがバッチリ理解できるようになりますよ!📝
それでは、早速見ていきましょう~!🎉
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
📚 質問に関する基本的な知識を深めたい方は、こちらの記事も参考にしてください:

質問の仕方の基礎知識🌟

まずは基本! 「質問にはどんな種類があるの?」 を一緒に見ていきましょう!💬
社会福祉士の現場では、質問を上手に使い分けることがとっても重要です。そこで押さえておきたいのが 「開かれた質問(オープン・クエスチョン)」 と 「閉ざされた質問(クローズド・クエスチョン)」 の違いなんです!
どちらも使い方次第で大きな力を発揮しますが、それぞれ特徴が異なります。簡単に言うと…
- 開かれた質問 → 相手が自由に答えられる質問
- 閉ざされた質問 → 「はい」「いいえ」や限られた答え方しかできない質問
それぞれの特徴をもう少し詳しく見ていきますね!💡
開かれた質問(オープン・クエスチョン)とは?✨
「開かれた質問」は、相手が 自由に考えたり感じたことを話す ことができる質問です!🌟 例えば…
- 「最近、どんなことが楽しいと感じますか?」
- 「今の暮らしで困っていることを教えてください!」
こんな質問をされたら、色んな答えが思い浮かびますよね?😊
答えが一つに定まらないので、相手の気持ちや考えを深く知ることができます!
🎯 ポイント
- 「なぜ?」「どのように?」といった言葉がよく使われる
- 相手の考えや気持ちを引き出したいときにピッタリ
閉ざされた質問(クローズド・クエスチョン)とは?
一方で「閉ざされた質問」は、「はい」「いいえ」や具体的な答えが一つだけ」 に絞られる質問です。例えば…
- 「あなたはご長男ですか?」
- 「こちらに住み始めたのはいつですか?」
こうした質問は、相手が詳しく考えなくても答えられるので、手早く情報を確認したいときに便利!💡
🎯 ポイント
- 「はい」や「いいえ」で答えられる形が多い
- 必要な情報を簡潔に聞きたいときに有効
これで「開かれた質問」と「閉ざされた質問」の基本的な違いがイメージできましたか?🤔✨
それぞれのメリットを押さえておけば、試験だけでなく実際の現場でも役立ちます!💪
社会福祉士試験で問われる「開かれた質問」と「閉ざされた質問」📝

社会福祉士国家試験では、質問の種類についての知識が重要視されます!💡 「質問なんて簡単でしょ~?」と思っていると、選択肢の中で迷子になってしまうことも…。😱 そこで、なぜこれらの質問が試験で問われるのか、その理由を一緒に見ていきましょう!
なぜ質問の種類が重要なのか?🤔
社会福祉士の仕事では、利用者の悩みや本音を引き出す ことが欠かせません。そのためには、相手が話しやすい質問を投げかけることがポイントです!💬
例えば、こんなシーンを想像してください。
利用者とのやり取り①:閉ざされた質問の場合
👩🦳「最近、ご飯はちゃんと食べられていますか?」
🧓「はい、食べています。」
閉ざされた質問では、話が「はい」「いいえ」で終わってしまいがちです。😓 これでは相手の状況を深く知ることができません…。
利用者とのやり取り②:開かれた質問の場合
👩🦳「最近、どんな食事を楽しんでいますか?」
🧓「そうですねぇ…最近はご飯がちょっと固く感じることが多いですね。でも、おかゆにすると美味しいです!」
開かれた質問なら、相手が具体的に話してくれる可能性がグッと高まります!😃💡 相手の生活や困りごとをしっかり聞き取れると、支援もスムーズに行えますよね。
試験では、こうした違いを踏まえて、質問の種類を見極める力が求められるのです!🔥
よく出題されるパターンとその攻略法🔑
試験で狙われるのは、「この質問はどちらに当てはまるか?」という判断問題です。例えば…
問題例
次の記述のうち、開かれた質問 に該当するものを選びなさい。
- 「こちらの施設に通い始めたのはいつですか?」
- 「今日のご気分はいかがですか?」
- 「結婚して、どんな変化を感じていますか?」
解答はズバリ…
- 正解:3
理由は簡単! 「どんな変化を感じていますか?」 という質問は、相手が自由に考えを話せるため「開かれた質問」に該当します!✨
試験問題に慣れるには、こうした選択肢の「判断基準」をきちんと押さえることが大事です。問題文を読んだら、「この質問に答えるパターンはいくつある?」と考えてみましょう!
📚 年金制度に関する重要な内容をもっと学びたい方は、こちらの記事もチェックしてみてください:

質問の具体例と解説🧐✨

ここからは、「開かれた質問」と「閉ざされた質問」の具体例を一緒に見ていきましょう!🚀 実際にどんな質問が試験や現場で使われるのかを知ることで、理解がグッと深まりますよ!
「開かれた質問」の具体例とその特徴🌟
「開かれた質問」は、利用者の気持ちや考えを詳しく聞き出したいときに使います。たとえば…
具体例
- 「最近どんなことが楽しいと思いますか?」
- 「今の暮らしでどんなことが困っていますか?」
- 「あなたのご家族について教えてください。」
こうした質問では、相手の答えが一つに定まりません。たくさんの情報を得ることができるので、相手が何を感じているか、どんなサポートが必要かが見えてきます!👓✨
具体例を使った解説
たとえば、「最近どんなことが楽しいと思いますか?」と質問した場合…。
🧓 利用者さん:「最近は孫が遊びに来てくれるのが本当に嬉しいんですよ。」
👩⚕️ 聞き手:「お孫さんとどんなことをしているんですか?」
🧓 利用者さん:「一緒に公園に行って遊んだり、お菓子作りをしたりしています。」
このように、質問をきっかけにどんどん話が広がります!🌈✨
「閉ざされた質問」の具体例とその特徴🛑
「閉ざされた質問」は、特定の情報を正確に聞き出したいときに便利です!💡 例えば…
具体例
- 「あなたはこの施設に何年通っていますか?」
- 「ご長男ですか?」
- 「食事は1日3回とっていますか?」
こうした質問は、答えが「○○です」と具体的に決まります。短い時間で正確な情報を得られるのが強みです!
具体例を使った解説
たとえば、「食事は1日3回とっていますか?」と質問した場合…。
🧓 利用者さん:「はい、3回食べています。」
👩⚕️ 聞き手:「どんな食事を召し上がっていますか?」(ここで開かれた質問を追加すると、さらに深い情報が得られます!)
このように、閉ざされた質問は「確認事項を短時間で押さえる」役割を果たします。⚡
どちらの質問もそれぞれの場面で役立つので、使い分けが大事です!🎯 ここまでで「具体例と特徴」のイメージができましたね!
理解を深めるための練習問題📚✏️

ここからは、「開かれた質問」と「閉ざされた質問」を実際に判断する練習問題を解いてみましょう!✨ 試験でもこのような形式で出題されることが多いので、しっかりトレーニングしておきましょうね!💪
選択問題で学ぶ質問の違い🔍
問題:次の記述のうち、「開かれた質問」に該当するものを 2つ 選びなさい。
- 「今日の朝ごはんは食べましたか?」
- 「最近、生活の中で感じていることを教えてください。」
- 「こちらの施設には、いつから通っていますか?」
- 「今の暮らしで、どんなサポートが必要だと思いますか?」
- 「体調は良いですか?」
答えを考えてみてください! 🤔✨
解答と解説
正解:2, 4
- 2.「最近、生活の中で感じていることを教えてください。」
→ 答えが一つに定まらず、相手の自由な考えを引き出す質問なので「開かれた質問」です!🎉 - 4.「今の暮らしで、どんなサポートが必要だと思いますか?」
→ 「どんなサポートが必要だと思いますか?」と尋ねているため、相手の意見を自由に聞くことができます。これも「開かれた質問」に該当します!😊
一方で…
- 1.「今日の朝ごはんは食べましたか?」
→ 「はい」または「いいえ」で答えられるので「閉ざされた質問」です。 - 3.「こちらの施設には、いつから通っていますか?」
→ 回答は「○年○月から」と一つに限られるため「閉ざされた質問」です。 - 5.「体調は良いですか?」
→ これも「はい」または「いいえ」で答えられるので「閉ざされた質問」です。
問題の解説で知識を強化💪
このように、「開かれた質問」か「閉ざされた質問」かを見分けるには、質問の回答がどれだけ自由か? を考えることがポイントです!✨
試験では選択肢の文章が長い場合もありますが、質問部分だけを冷静に判断すれば間違えにくくなります!💡 ぜひ、問題文をしっかり読み込む練習を積みましょう!
これで「練習問題を解いて学ぶ」セクションは終了です!📝✨
次は、質問を実務でどう活かせるかについて解説していきます!
開かれた質問と閉ざされた質問を実務に活かす✨

試験対策だけでなく、実際の社会福祉の現場でも「開かれた質問」と「閉ざされた質問」をうまく使い分けることで、利用者とのコミュニケーションがより良いものになります!💬✨ ここでは、その具体的な活用方法について解説していきます!
利用者とのコミュニケーションに活かす方法🌈
現場では、相手の状況や気持ちを理解し、最適なサポートを提供することが求められます。そのためには、質問の使い方がカギ となります!🔑
開かれた質問を使う場面
- 相手の気持ちや考えを深く知りたいとき
- 問題の背景や原因を探るとき
- 利用者に自由に話してもらいたいとき
例: 「どんなことに困っていますか?」、「その出来事をどう感じましたか?」
閉ざされた質問を使う場面
- 特定の情報を短時間で確認したいとき
- 利用者が話しにくそうなとき
- 医療や施設利用の状況を聞き取るとき
例: 「今日は体調が良いですか?」、「こちらのサービスをご利用になったことはありますか?」
コツと注意点
- 開かれた質問は、傾聴 を意識することが大切!相手が話した内容に耳を傾け、必要に応じて深掘りしましょう。👂✨
- 閉ざされた質問だけを使うと、会話が「はい」「いいえ」で終わってしまいがちです。適度に開かれた質問を交えるのがポイント!
カウンセリングや面談での具体例🎙️
カウンセリングや面談では、利用者の心理的負担を減らすためにも、質問の種類を慎重に選ぶ必要があります!💡
ケーススタディ:高齢者の面談
👩⚕️:「最近、ご家族とどんな話をされていますか?」(開かれた質問)
🧓:「うーん、あまり最近は話していないですね。」
👩⚕️:「最近はお忙しいんですか?」(閉ざされた質問で具体的な理由を探る)
🧓:「そうですね。仕事が忙しいみたいで…。」
このように、開かれた質問と閉ざされた質問を組み合わせることで、より詳細な情報を引き出すことができます!✨
これで、「質問を実務に活かす方法」の解説は終了です!🙌
現場での活用を意識しながら、日々の学習に役立ててくださいね!😊
まとめ|質問の種類を理解して社会福祉士国家試験に挑もう!💪✨
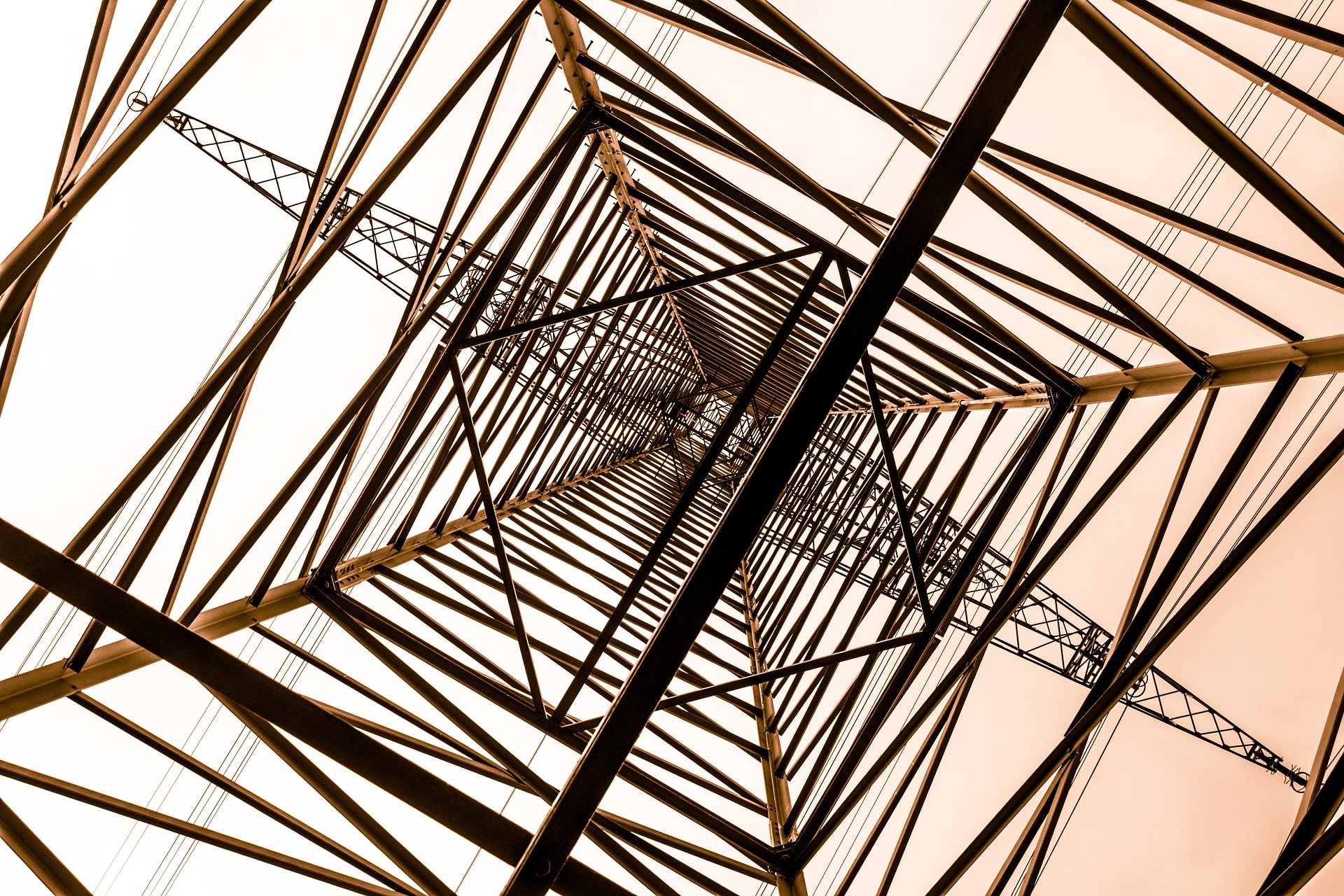
ここまで、「開かれた質問(オープン・クエスチョン)」と「閉ざされた質問(クローズド・クエスチョン)」の違い、試験対策、実務での活用法について詳しく解説しました!🎉
重要ポイントの復習📚
- 開かれた質問 は自由な回答を引き出すため、相手の気持ちや考えを深掘りするのに適しています!
- 例:「どんなことが楽しいと感じますか?」
- 閉ざされた質問 は具体的な情報を短時間で得るために効果的です!
- 例:「今日は体調が良いですか?」
社会福祉士国家試験では、質問の種類を問う問題が頻出です。試験勉強の段階でしっかり違いを理解しておくと、実務でも役立つスキルになります!💼✨
次のステップ🌟
この記事で学んだ内容を生かし、まずは練習問題をたくさん解いてみましょう!さらに、実際に質問の使い方をシミュレーションしてみると、理解が深まりますよ!💡
社会福祉士国家試験は、知識を活用する力が試されます。今回の記事を参考に、効率的に学習を進めてくださいね!📖✨
「参考書や問題集だけでは不安…」という方も大丈夫!福祉イノベーションズ大学では、実践的な情報をどんどん発信しています。引き続き一緒に頑張りましょう!💪✨
この記事を読んで、「質問の違い、よくわかったよ!」と思えたら、ぜひシェアやコメントで教えてくださいね~!😊
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
<この記事のQ&A>🧐💡

Q1. 「開かれた質問」と「閉ざされた質問」の違いは何ですか?
A1. 開かれた質問(オープン・クエスチョン)は、相手が自由に答えられる質問で、気持ちや考えを深く知るのに適しています。一方、閉ざされた質問(クローズド・クエスチョン)は、「はい」「いいえ」や具体的な答えが決まっている質問で、短時間で情報を得たいときに便利です。
Q2. 社会福祉士国家試験ではどのような問題が出ますか?
A2. 試験では、「この質問は開かれた質問か、閉ざされた質問か?」を判断させる問題がよく出題されます。選択肢を読んで、質問の回答が一つに定まるかどうかを見極めるのがポイントです!
Q3. 実務ではどちらの質問が多く使われますか?
A3. 実務では、利用者の状況や気持ちを詳しく知りたいときは開かれた質問、短時間で具体的な情報を得たいときは閉ざされた質問が使われます。状況に応じて使い分けるのがベストです!
Q4. 質問の種類を判断するコツはありますか?
A4. 質問に対する答えが「はい」「いいえ」で終わる場合は閉ざされた質問、それ以外に自由に答えられる場合は開かれた質問と判断できます。また、「なぜ」「どのように」といった表現が含まれる場合は、開かれた質問であることが多いです。
Q5. 練習問題をもっと解くにはどうすればいいですか?
A5. 福祉関連の問題集や模擬試験を活用するのがおすすめです。また、日常生活で家族や友人に質問を投げかけて、実践的に練習するのも良い方法です!




















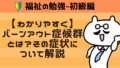
コメント