みなさん、こんにちは!いっちー教授です!✨
今日もテンションMAXで、社会福祉士国家試験に役立つ知識を楽しく学んでいきましょう!🙌
今回のテーマは、 「日本の昔にあった5つの制度」 について!💡
「えっ、昔の制度なんて今と何が関係あるの?」と思うかもしれませんが、これが実は 福祉のルーツ を学ぶ大切なチャンスなんです!🚀
社会福祉士国家試験では、日本の歴史に根付いた仕組みや制度についても出題されます。それを知っていると、 福祉の本質 を理解するうえで大きな武器になります!🛡️
🎯 この記事のポイント
- 試験に出る5つの制度を わかりやすく解説
- 制度が生まれた背景や仕組みを 小学生でもわかる例 で説明
- 現代に繋がる福祉の仕組みとの 共通点を発見
それでは、元気よくスタートしましょう!✨
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
日本の昔の制度について学ぼう🌸

みなさん、昔の日本には今とは少し違う 「助け合いの仕組み」 が存在していました。その仕組みが、今の福祉制度の元になっていることもあるんです!😲
たとえば、あなたが友達とお互いに「困ったら助け合おう!」と約束しているとしますよね。それが、今から紹介する制度の考え方に似ているんです。
「助け合い」「協力し合い」「困ったときはお互いさま」ーーそんな温かい気持ちが制度として形になっていました。💖
そして、それらの制度がどんなものだったのかを知ることが、国家試験の対策だけでなく、 福祉への深い理解 にもつながるんですよ!
社会福祉士国家試験で問われる「昔の制度」とは?📚

社会福祉士国家試験では、日本の歴史における 福祉や救済の仕組み がテーマになることがあります。これらの制度は、現代の福祉政策と比べて「こういうところが似ているんだ!」と発見できるヒントがいっぱい!✨
例えば、こんな出題が予想されます:
「結(ゆい)はどのような特徴を持つ制度か?」
「七分積立金制度と現代の税制度の違いは?」
試験対策として、このような制度の 特徴や背景 をしっかり押さえることが重要です!🚀
なぜこれらの制度を学ぶ必要があるのか?🤔

さて、ここで疑問に思う人もいるかもしれません。
「昔の制度なんて、国家試験と関係あるの?今の福祉制度を学ぶだけでよくない?」
結論を言うと、 めちゃくちゃ関係あります! 🌟
なぜなら、昔の制度は現代の福祉の「根っこ」に当たる部分だからです。例えば、福祉とは 「困った人を助ける仕組み」 のこと。日本の昔の制度も、まさにそれを目的として作られていました。
これを知ると、現代の福祉制度がどうして今の形になったのかがよくわかります。📖
さらに、試験ではこうした制度の名前や内容がそのまま出題されることもあるので、 学んでおいて損はありません! 💯
日本の昔にあった5つの制度🌟
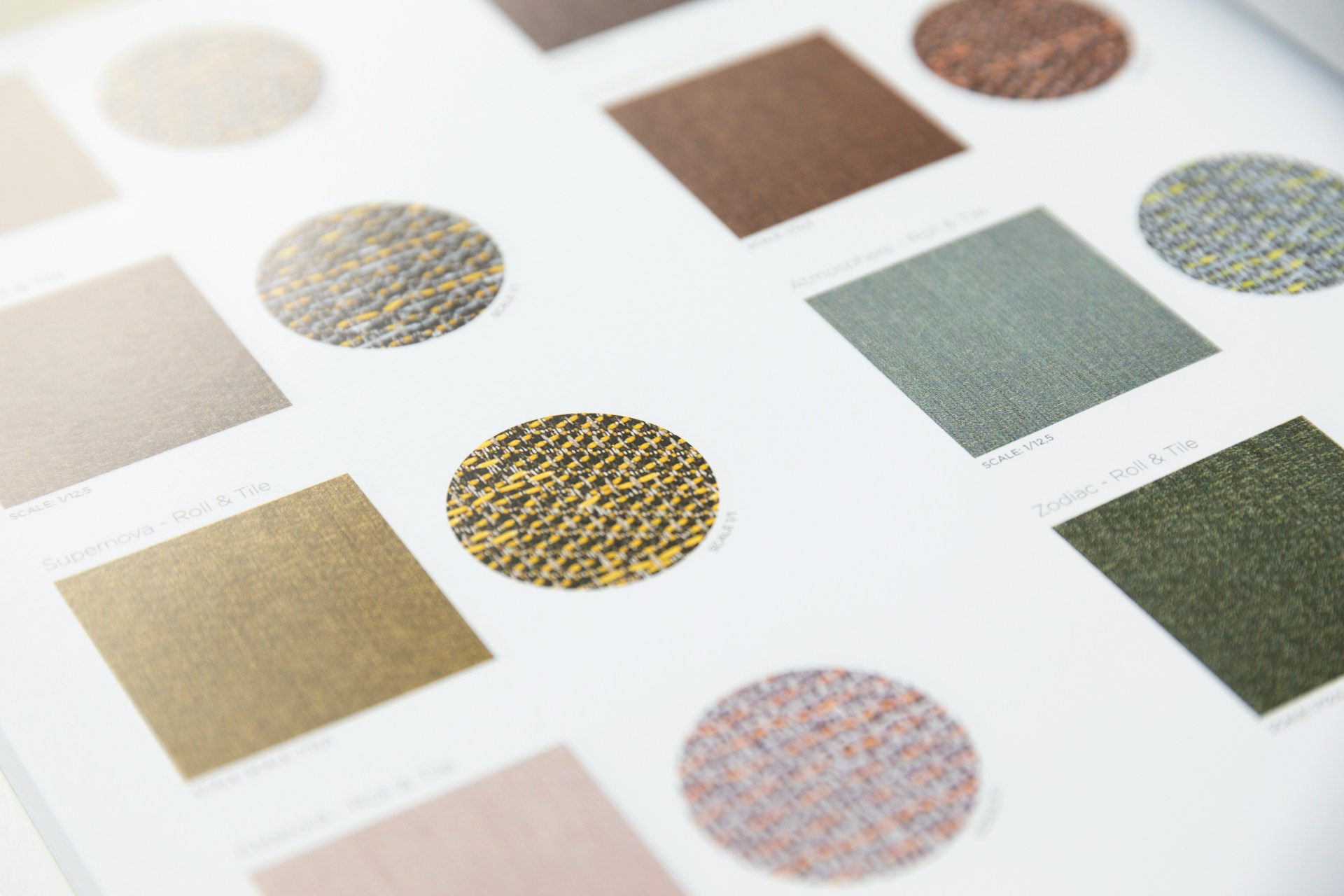
それでは、ここからは 日本の昔にあった5つの制度 を具体的に見ていきましょう!👀
結(ゆい)とは?地域で支え合う共同労働🤝
まずご紹介するのは、「結(ゆい)」です!
これは田植えや収穫といった 一時的に多くの人手が必要になる作業 を助け合うために、地域の人々が協力する仕組みでした。
🌾 具体例でイメージ!
田植えを一人で全部やるのって大変ですよね?😵
でも、「結」の仕組みでは、村の仲間みんなで集まって助け合いながら田植えを進めました。そして、別の日にはまた別の家の田植えを手伝うんです。
まさに 「助け合いの精神」 が生んだ仕組みですね!✨
🌟 現代の福祉との共通点
今で言うと、自治会やボランティア活動が「結」に近いかもしれません。例えば、地域の清掃活動などでみんなが協力する感じ、あれが「結」の考え方なんです!🌱
頼母子講(たのもしこう)とは?経済的救済を目的とした組織💰
次に登場するのは、「頼母子講(たのもしこう)」です!
これは、みんなでお金を出し合って、困ったときにそのお金を活用する仕組み。現代でいうところの 「共済」や「信用組合」 に似た制度です。
💸 具体例でイメージ!
例えば、5人の仲間がそれぞれ月1万円を出し合ったとします。毎月5万円が集まるので、そのうち1人がその5万円を受け取ります。次の月もまた5万円が集まり、別の1人が受け取る…という仕組みです。
これなら、少額ずつでも大きな金額を一度に使えるチャンスがあるんです!💪
🌟 現代の福祉との共通点
この仕組みは、現代の医療共済や保険制度に似ていますね!「みんなで支え合うことで、誰かがピンチのときに助けられる」という考え方が生きています。🌈
七分積立金制度とは?凶荒時の救済を支える仕組み🌟
次にご紹介するのは、「七分積立金制度」です!この制度は、 松平定信 が考案したもので、住民から集めたお金の一部を積み立てて、凶作や災害などの非常時に備える仕組みです。💰🌾
🏰 背景を少し説明!
この制度ができたのは江戸時代の中期。当時、飢饉(ききん)などで苦しむ人々が多かったため、 「平常時に備えをしよう!」 という発想で作られたんです。
🌟 具体例でイメージ!
例えば、村の全員がそれぞれ収入の7分の1を積み立てます。そのお金を蓄えておいて、災害や不作で生活が苦しくなったときに、その積立金を使って助け合うのです。これにより、 飢えや貧困に苦しむ人を支援 することができました!
🌟 現代の福祉との共通点
この制度は、現代の税金や社会保険制度に似ています。みんなでお金を少しずつ出し合い、困った人を支えるという発想が共通しているんですね!✨
五保の制とは?近隣住民の協力による治安維持と納税制度🚨
続いてご紹介するのは、「五保の制」です!この制度は、近隣の 5戸 をひとまとめにして、みんなで協力して治安を維持したり、納税を行ったりする仕組みでした。🏠💂
🏡 具体例でイメージ!
イメージしてみてください。ある村に5軒の家があるとします。それを1グループとしてまとめ、そのグループ全体で「税金の支払い」や「犯罪防止の監視」を行います。もし1軒がルールを破ったら、グループ全体で責任を取る仕組みだったんです。
🌟 現代の福祉との共通点
この制度の考え方は、今も地域社会に残っています。「町内会」や「自治会」の活動で、みんなが協力して防犯や地域清掃を行うことに似ていますね!🚶
戸令(こりょう)とは?親族間相互扶助を重視した仕組み👨👩👧👦
最後にご紹介するのは、「戸令(こりょう)」です!これは、救済が必要な人を助けるときに、まずは 親族間 で助け合うことを重視する仕組みです。
🏡 具体例でイメージ!
例えば、ある家族の誰かが病気で仕事ができなくなった場合、まずはその人の親族(おじいさんやおばさんなど)が支援します。それでも無理な場合は、近隣住民や村が助けるという流れです。
🌟 現代の福祉との共通点
この仕組みは、現代の民法で定められた 「親族間の扶養義務」 に似ていますね!例えば、親が生活に困った場合、子どもが助ける義務がある、という考え方に通じています。💞
🌟 5つの制度のまとめ!
ここまで紹介してきた5つの制度をまとめるとこんな感じです:
- 結(ゆい) :地域で協力して共同作業を行う仕組み
- 頼母子講(たのもしこう) :みんなでお金を出し合い、必要な人を支援する仕組み
- 七分積立金制度 :非常時に備えてお金を積み立てる仕組み
- 五保の制 :近隣住民で治安維持や納税を協力して行う仕組み
- 戸令(こりょう) :親族間の助け合いを重視した救済制度
これらの制度は、日本の「助け合いの精神」をよく表していますね!💖
各制度を理解するためのポイント🔍

ここからは、5つの制度をもっと深く理解するためのポイントをお伝えします!🙌
「覚えるだけでは試験に活かせない!」という方に向けて、わかりやすく解説していきますよ!✨
時代背景を押さえよう📜
まず重要なのは、 制度が生まれた背景を知ること です!🌟
たとえば、次のような視点で考えてみてください:
- 結(ゆい): 農作業が中心だった時代、人手が不足すると村全体が困る!だからこそ助け合いが必要だった。
- 七分積立金制度: 飢饉や災害に備える仕組みがなければ、多くの人が命を落とすことに…。
当時の人々が 何を大切にしていたのか を考えると、それぞれの制度が作られた理由が見えてきます。
現代の制度と共通点を見つける🌐
次に、現代の福祉制度と昔の制度を比べてみましょう!💡
🌟 具体例で考えよう!
- 結と現代のボランティア活動: 助け合いの精神は変わらない!
- 七分積立金制度と社会保険: どちらも「みんなで支える」仕組み。
こうして共通点を見つけると、試験での記憶がより鮮明になります!💡
社会福祉士国家試験対策に役立つ学び方📘

最後に、これらの制度を試験で活かすための学び方をご紹介します!✨
ただ覚えるだけではなく、理解を深めて実践的な知識にするコツを伝授しますよ!💪
基本問題を活用して知識を整理しよう📝
過去問題や模擬試験で「基本問題」を繰り返し解くのが効果的です!📚
例えば、次のような問題を解いてみましょう:
問:次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 結は、田植えの時期に大勢の人出を必要とする際に助け合う共同労働のことである。
- 頼母子講は、天皇による儒教的政策のことである。
- 七分積立金制度は、貧民救済を目的とした地域の集まりを指す。
- 五保の制は、親族間で助け合う仕組みである。
答え:1
こういった問題を繰り返すことで、 「どこが間違っているのか?」 を見つけられる力がつきます!💡
実際の試験で問われた内容を徹底分析🔍
社会福祉士国家試験では、「背景」「目的」「仕組み」のどれかが問われます。以下のような分析が役立ちます:
- 背景: 制度が生まれた時代の状況は?
- 目的: 何を解決するために作られたの?
- 仕組み: 誰が、どのように関わっていた?
🌟 例:頼母子講の分析
- 背景: 金融制度が発展していない時代。
- 目的: 少額を出し合い、まとまったお金を使える仕組みを作る。
- 仕組み: 複数人でお金を出し合い、順番にそのお金を受け取る。
このように整理していくと、「暗記」ではなく「理解」に繋がります!💪
まとめ:日本の昔の制度を理解して試験対策に活かそう🌟

日本の昔の制度は、 福祉のルーツ を学ぶ絶好のチャンスです!✨
- 「結」で助け合いの精神を学び、
- 「七分積立金制度」で備える大切さを知り、
- 「戸令」で親族間の支援の意味を考える。
これらをしっかり理解して、 社会福祉士国家試験 を突破しましょう!🚀
<この記事のQ&A>💡

Q1. 結(ゆい)は現代のどのような仕組みに似ていますか?
A1. 結は現代のボランティア活動や地域の共同作業(自治会や町内会の清掃活動など)に似ています。みんなで助け合うという精神が共通していますね!🤝
Q2. 頼母子講(たのもしこう)はどんな目的で作られた制度ですか?
A2. 頼母子講は、みんなで少しずつお金を出し合い、必要な人がそのお金を受け取ることで、生活を支える制度です。現代の共済保険や信用組合のような役割を持っていました!💰
Q3. 七分積立金制度は現代のどの仕組みに似ていますか?
A3. 七分積立金制度は、現代の税金や社会保険制度に似ています。住民がお金を積み立て、非常時や災害時の救済に活用される点が共通しています!🌟
Q4. 五保の制で重視されたことは何ですか?
A4. 五保の制では、近隣の5戸を一つの組としてまとめ、納税や治安維持をグループで責任を持つ仕組みが重視されていました。この仕組みは、地域での連帯感を生む重要な役割を果たしていました!🚨
Q5. 戸令(こりょう)とはどのような考え方の制度ですか?
A5. 戸令は、まず親族間で助け合い、その後に近隣住民が支援するという仕組みです。現代の親族間の扶養義務に似た考え方が特徴です!👨👩👧👦





















コメント