こんにちは、福祉イノベーションズ大学の いっちー教授 です!✨
今日もみなさんと一緒に、社会福祉士国家試験に合格するための大事なポイントをガッツリ学んでいきますよ~!💪🎓
さて、みなさんは「シーボーム報告を含む5つの報告」って聞いたことがありますか?🤔
これ、社会福祉士国家試験では 超重要 なテーマなんです。
「報告書っていくつもあって覚えられないよ~😱」って方、安心してください!
今回は、誰でも覚えられるように めちゃくちゃ簡単に、わかりやすく 解説していきます。
テンションMAXでやる気スイッチONしていきましょう!🔥
それでは、早速スタートです!🚀
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
📚 社会福祉士試験に頻出の福祉三法・六法・八法の成り立ちや重要年号を楽しく学びたい方は、こちらの記事もご覧ください:

社会福祉士試験に出る「5つの報告」とは?

社会福祉士国家試験では、「シーボーム報告」や「バークレイ報告」といった報告書がよく出題されます。これらは、イギリスで社会福祉の仕組みを考え直した際に作られた報告書で、それぞれに特徴や重要な提言があります。🌍
たとえば、「シーボーム報告」は 包括的なサービス を目指したもので、「バークレイ報告」は コミュニティソーシャルワーク を提案しています。
一つひとつを理解するのは大変そうに見えるけど、心配いりません!✨
覚えるコツは「具体例」と「ポイントを絞ること」!
これから、5つの報告の内容と覚え方をテンション高めで解説していきます!😆
さぁ、行きますよ~!次の章から順番に見ていきましょう!🎉
📚 シーボーム報告を含む5つの報告の歴史的背景や改正ポイントを詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください:

シーボーム報告(1968年):すべてを「しぼ~ん」とひとまとめに!

シーボーム報告、名前だけだと何のことかピンとこないですよね?🤔
でも、安心してください!これ、覚え方のポイントがあるんです!
包括的アプローチとは何か?
シーボーム報告では、福祉サービスを 高齢分野、障害分野、児童分野 といった専門ごとに分けるのではなく、 全部ひとつにまとめるべき! と提案しました。
なぜそんなことを考えたのかというと…。
問題の背景:「制度の狭間にいる人」って?
たとえば、高齢者でありながら障害を持っている方を想像してみてください。👵♿
高齢者向けのサービスだけでは足りず、障害分野の専門知識も必要です。
けれど、分野ごとに支援がバラバラだと、その人にぴったりのケアが受けられないんです!💦
こうした 「制度の狭間」に取り残される人たち を減らすために、すべてを包括的に扱おう!とシーボーム報告は訴えたんです。
覚え方のコツ:「専門をしぼ~んと統合する」
「分野をひとつにまとめる」イメージで シーボーム=しぼ~ん って覚えましょう!🎈
これなら絶対忘れません!
ポイント 🌟
- 分野を分けるのではなく、すべてひとつにまとめた包括的な支援が必要!
- 「制度の狭間」にいる人たちへのケアを重視!
どうですか?シーボーム報告のイメージ、つかめましたか?✨
エイブス報告(1969年):ボランティアの力を最大限に活用しよう!
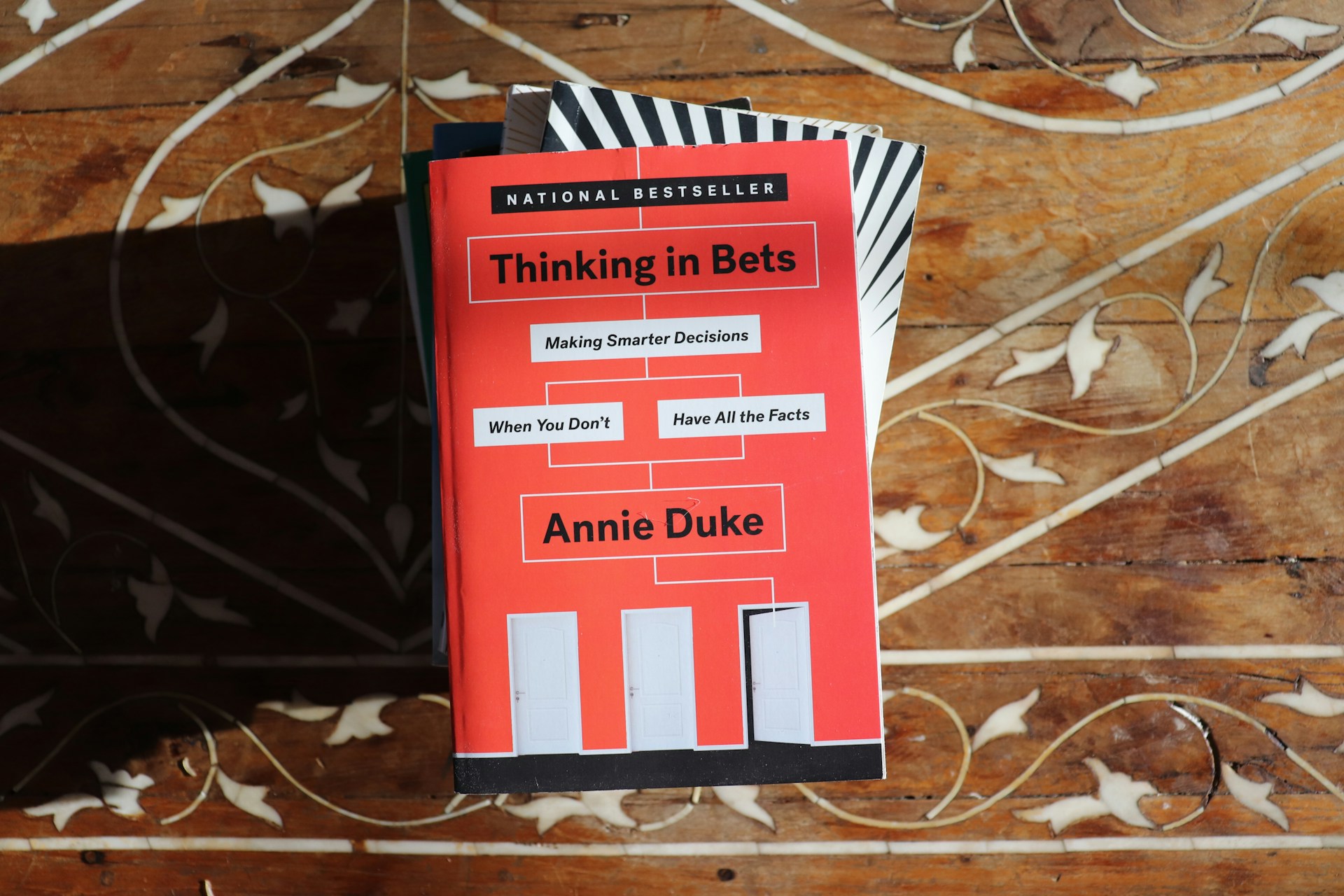
次に紹介するのは エイブス報告 です!📢
ボランティア活動って、今やどこでも耳にしますが、その大切さを改めて示したのがこの報告です。
ボランティアの役割とは?
エイブス報告では、社会福祉分野での ボランティアの役割 が強調されています。
たとえば、阪神淡路大震災の時を思い出してみてください。1995年、全国から多くのボランティアが被災地に駆けつけ、支援活動を行いました。🚑💪
エイブス報告は、「こうしたボランティアの力は、専門職ではできない新しい社会サービスを生む原動力になる」と言っています。
「ボランティアが何かを押し付けられるのではなく、自分たちで新しい価値を創造することが重要なんだ!」と提言しているんです。
日本の事例:特定非営利活動促進法(NPO法)
日本では、このエイブス報告の精神に通じるような法律があります。それが 特定非営利活動促進法(NPO法) です!🇯🇵✨
1998年に施行されたこの法律では、ボランティア活動を法人化し、支援を行う仕組みが作られました。
たとえば、環境保護を進める団体や、地域の高齢者を支援する団体などが、NPO法人として活動しています。
覚え方のコツ:「エイブス=エールを送るボランティア」
「エイブス報告はボランティアを応援している!」と覚えれば、試験でもバッチリですね!💯
ポイント 🌟
- ボランティアの役割は「専門職ではできない新しいサービスを作ること」!
- 日本のNPO法ともつながる重要な考え方!
ボランティアの力、すごいですよね~!🙌
ウェルフェンデン報告(1978年):福祉サービスを多元的に考えよう!
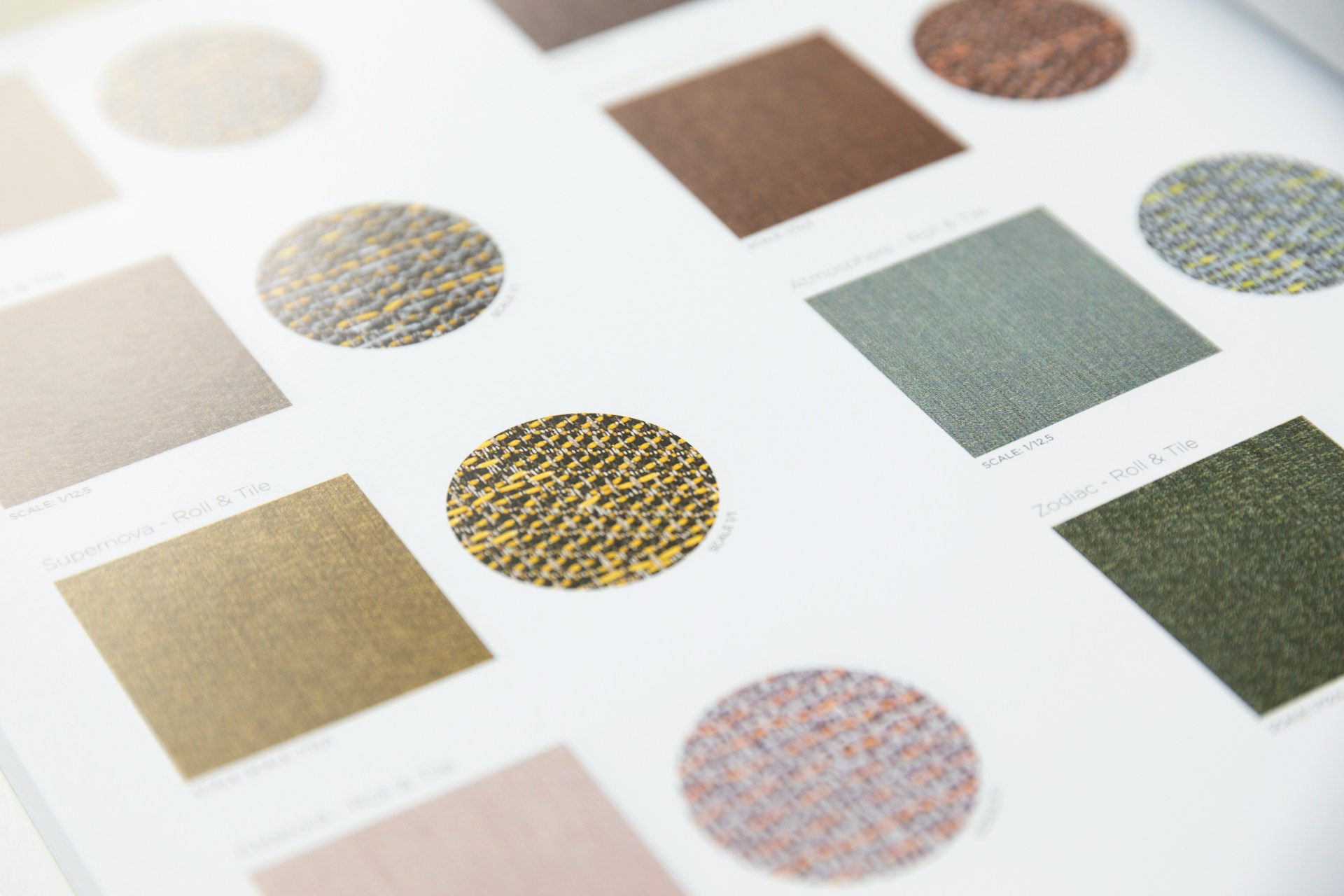
さあ次は、 ウェルフェンデン報告 の登場です!📖✨
この報告では、社会福祉サービスをどうやって提供すれば良いのか、その「供給システム」に注目しています。
福祉多元主義ってなに?
ウェルフェンデン報告は、福祉サービスを 4つの部門 に分けて考えました。以下がその内訳です!👇
- インフォーマル部門:家族や友人、近隣の助け合い
- 公的部門:自治体や政府によるサービス
- 民間営利部門:民間企業が提供する福祉サービス
- 民間非営利部門:NPOやボランティア団体など
これを総称して「福祉多元主義」と呼びます!💡
「いろんな人や組織が力を合わせて福祉を支えるべき!」という考え方ですね。
インフォーマルネットワークとは?
ここで重要なのが インフォーマルネットワーク。
これは、家族や友人、近所の人たちがつながることでできる助け合いの輪のことです。
たとえば、おばあちゃんが病気になった時に、家族が世話をするのはもちろん、近所の人が「おかゆを届けてあげる」といった行動もインフォーマルネットワークの一例です。👵🍲
ウェルフェンデン報告では、この インフォーマルなつながりが福祉を支える重要な役割を果たす と述べています。
覚え方のコツ:「ウェルフェンデン=福祉のウェルカムな多元主義」
ウェルフェンデン報告を「みんなウェルカム!多元的な福祉を作ろう!」とイメージすると覚えやすいですよ!🙌
ポイント 🌟
- 福祉サービスを4つの部門に分け、全体で支える仕組みを提唱!
- 家族や地域の助け合い(インフォーマルネットワーク)がカギ!
これでウェルフェンデン報告も完璧ですね!✨
バークレイ報告(1982年):地域に寄り添う「コミュニティソーシャルワーク」
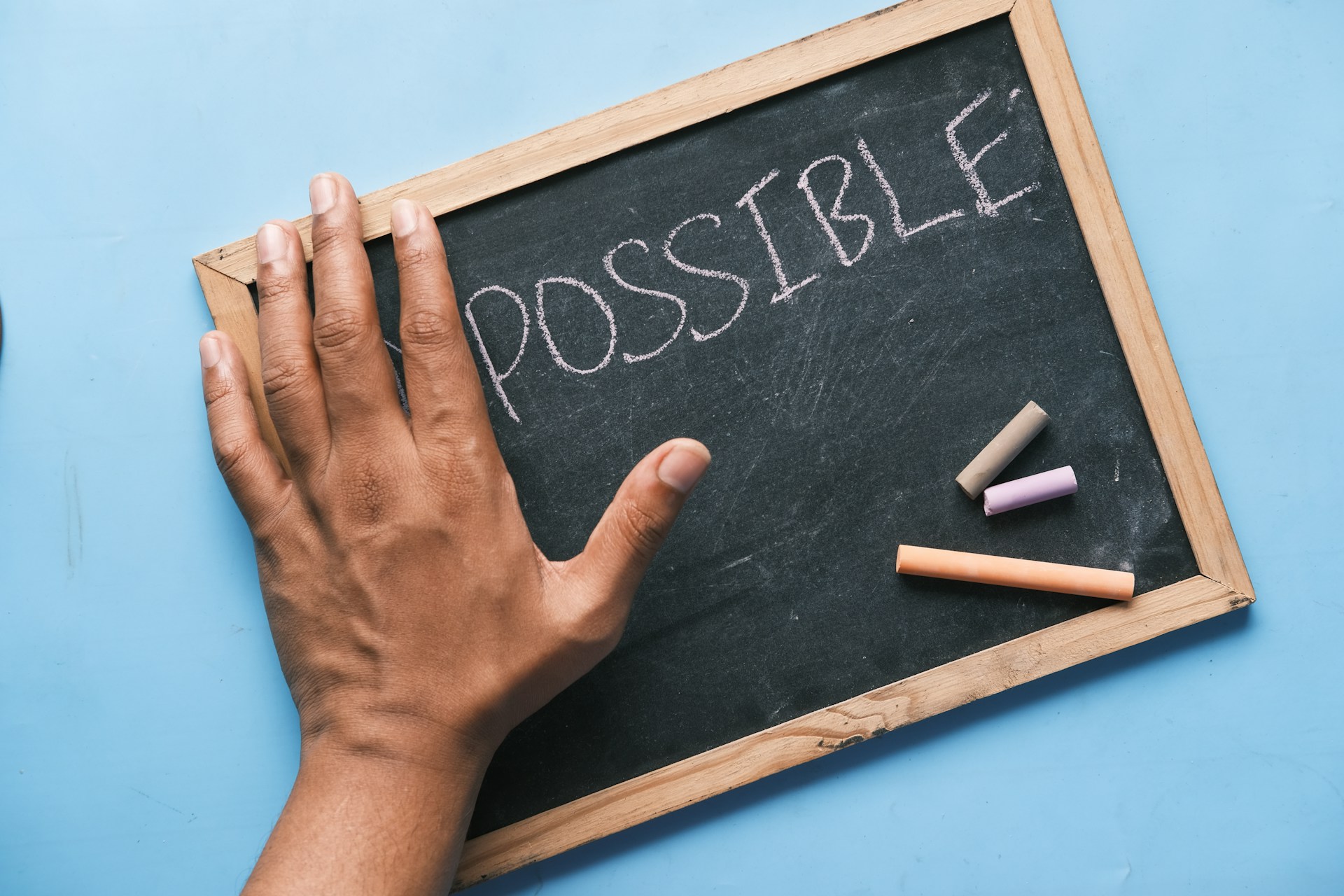
次に取り上げるのは バークレイ報告 です!🎉
この報告では、ソーシャルワーカーの新しい役割について、具体的な提案がなされました。
コミュニティソーシャルワークとは?
バークレイ報告が提唱したのは、「コミュニティソーシャルワーク」という新しい実践方法です!
これ、何が新しいのかというと…。
従来のソーシャルワークでは、 ケースワーク(個人を対象にした支援)や グループワーク(小グループでの支援)といった方法が主流でした。
しかしバークレイ報告は、これらを 統合 し、さらに地域全体に働きかける「コミュニティ基盤」の方法を提案したんです!
たとえば、地域で高齢者が孤立している問題に対して、
- 個別に相談に乗る(ケースワーク)
- 同じ悩みを持つ高齢者同士を集める(グループワーク)
- 地域のコミュニティを活性化させる(コミュニティソーシャルワーク)
このように、ケースワークやグループワークを活用しつつ、地域全体を巻き込むアプローチが コミュニティソーシャルワーク です!🌟
間接援助と直接援助の違いとは?
バークレイ報告を理解するうえで重要なのが 直接援助 と 間接援助 の違いです。
- 直接援助:困っている本人(クライエント)に直接働きかけること。
例:おばあちゃんに訪問して、生活の相談に乗る。👵💬 - 間接援助:周囲の環境に働きかけて、支援しやすくすること。
例:地域の自治会に協力をお願いし、高齢者が安心して暮らせる仕組みを作る。🏘️
バークレイ報告は、 直接援助と間接援助を統合した実践 を提唱しています!
覚え方のコツ:「バークレイ=地域にバーンと寄り添う!」
「バークレイ報告=地域を基盤にした支援」って覚えると忘れません!😄
ポイント 🌟
- 従来のケースワーク・グループワークを統合!
- 地域全体に働きかける「コミュニティソーシャルワーク」を提案!
これでバークレイ報告のイメージもバッチリです!🎯
グリフィス報告(1988年):地域ケアを進めるための計画を作ろう!

最後にご紹介するのは グリフィス報告 です!🎉
この報告は、地域ケア(コミュニティケア)を推進するために必要な仕組みについて提案した、とても重要な内容です。
コミュニティケアとは?
まず、「コミュニティケアって何?」という疑問を解決しましょう!🧐
これは、 高齢者や障害を持つ方々が施設ではなく、地域社会の中で暮らしながら支援を受けられるようにする仕組み のことです。
たとえば、高齢者が特別養護老人ホームに入所する代わりに、地域の中でデイサービスや訪問介護を利用して暮らし続けられるようにすること。これがコミュニティケアの考え方です!🏠👵
「施設から地域へ」の流れを支えるためには、 地域社会がケアを受け入れる体制を整えること が必要なんです。
財政の仕組みが必要!
でも、ここで問題が発生します…。💸
「地域でケアをするのって、お金がかかるよね?」
そうなんです!施設の中なら人材も設備もまとまっていますが、地域で同じようなケアをするには、より多くの人手やサービスが必要になります。
そこでグリフィス報告では、 地方自治体がコミュニティケア計画を作る ことを提案しました!
計画を立てて、どこにお金をかけるべきか、どのようにケアを提供するのかをしっかり決めよう!というわけですね。
覚え方のコツ:「グリフィス=グリッと計画を立てよう!」
グリフィス報告は「地域ケアのために計画を作る」がキーワードなので、計画づくりの重要性を意識して覚えましょう!📋✨
ポイント 🌟
- 地域ケア=施設から地域社会へ支援の場を移す考え方!
- コミュニティケアを進めるには、自治体による計画づくりが必須!
これでグリフィス報告もマスターできましたね!💪✨
まとめ:5つの報告をしっかり理解して国家試験対策を万全に!

ここまで、社会福祉士国家試験に出題される 5つの報告 をテンションMAXで解説してきました!🎉
それでは最後に、重要なポイントを一気に振り返っていきましょう!
おさらい!5つの報告のキーワード
- シーボーム報告(1968年)
- 包括的アプローチ を目指す報告!
- 高齢分野や障害分野などをひとまとめにして支援を届ける!
- エイブス報告(1969年)
- ボランティアの役割 を強調!
- 「新しい社会サービスを作る原動力はボランティアだ!」
- ウェルフェンデン報告(1978年)
- 福祉多元主義 を提唱!
- 家族や地域、民間企業、行政など、みんなで支える福祉の仕組み!
- バークレイ報告(1982年)
- コミュニティソーシャルワーク を提案!
- 地域全体を巻き込む支援が大切!
- グリフィス報告(1988年)
- コミュニティケアの計画 を提案!
- 地域で支えるために、財政と計画を整えよう!
試験対策のコツ
報告ごとの特徴をイメージで覚えると、試験でも迷わず解答できるようになります!💯
たとえば…
- シーボーム報告:「分野をしぼ~んと統合!」
- エイブス報告:「ボランティアが新しいサービスを作る!」
- ウェルフェンデン報告:「みんなでウェルカムな福祉を!」
- バークレイ報告:「地域にバーンと寄り添う!」
- グリフィス報告:「グリッと計画を立てる!」
ちょっとした語呂合わせやイメージが、記憶を助けてくれますよ!
💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!
いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇
🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/
「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇
📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/
📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3
<この記事のQ&A>

ここでは、この記事で扱った内容に関するよくある質問をまとめました!📚✨
試験対策や実際の学びに役立つ情報を再確認していきましょう!
Q1. シーボーム報告の「包括的アプローチ」って、具体的には何を指しますか?
A1. 包括的アプローチとは、高齢分野や障害分野などを分けずに、1つの部局で統合的に支援を行う方法です。
たとえば、高齢者でありながら障害を持つ人へのケアが、どちらの分野でも対応可能になる仕組みを作ることを指します。
Q2. エイブス報告の「ボランティアの役割」ってどんなものですか?
A2. エイブス報告では、ボランティアは「専門職にはできない新しい社会サービスを作る役割がある」と提言しています。
具体例として、日本の阪神淡路大震災(1995年)後のボランティア活動が挙げられます。これを機にボランティアの重要性が広まり、NPO法が生まれました。
Q3. ウェルフェンデン報告が提唱した「福祉多元主義」とは何ですか?
A3. 福祉多元主義は、福祉を提供する主体を4つに分けて、それぞれが協力し合う仕組みです。
- 家族や友人(インフォーマル部門)
- 政府や自治体(公的部門)
- 民間企業(民間営利部門)
- NPOやボランティア(民間非営利部門)
これらが連携して地域ケアを支えることが重要とされています。
Q4. バークレイ報告で言う「コミュニティソーシャルワーク」って何が新しいんですか?
A4. コミュニティソーシャルワークは、ケースワークやグループワークといった伝統的な援助技術を統合し、地域全体を基盤にして支援する方法です。
個別の支援だけでなく、地域全体の課題を解決するために働きかける点が新しいアプローチです。
Q5. グリフィス報告の「コミュニティケア計画」って何のために必要なんですか?
A5. コミュニティケア計画は、施設ではなく地域社会でケアを行うために必要な財政とサービスの仕組みを整えるための計画です。
「どこにお金をかけるか」「どんなサービスが必要か」を地方自治体が計画し、地域ケアの実現を進めることを目指しています。





















コメント