今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて一緒に勉強していきましょう!今回のテーマは、「【一から学ぼう】更生保護制度についてわかりやすく解説」です。では、授業を始めていきましょう。

*今回の記事の構成として、初めに更生保護制度に関する基本問題を出題します。その後、問題の解答解説を行い、理解が深められる構成になっています。
問)次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1.更生保護制度を基礎づけているのは、少年法である。
2.更生保護制度は、刑事政策における施設内処遇を担っている。
3.更生保護の目的は、犯罪及び非行を行うおそれのあるものに対して適切な予防活動を行うことにより犯罪を防ぎ、またはその非行性をなくし、自立と改善更生を助けることである。
4.更生保護に関する事務は家庭裁判所が行なっている。
5.更生保護の対象者は、保護観察に付されているものに限らない。
答え)5.更生保護の対象者は、保護観察に付されているものに限らない。

なので、まずは基礎の基礎から学習していきましょう。

1限目:更生保護制度は更生保護法に規定されいている
まず、更生保護制度がどのような制度なのか?についてわかりやすく解説していきます。
先ほどの選択肢「1」を見ていきましょう。
1.更生保護制度を基礎づけているのは、少年法である。
この選択肢は、不正解です。
更生保護制度は、少年法に規定されているのではなく、「更生保護法」と呼ばれる法律が根拠法となっています。

2限目:更生保護法の目的は社会内処遇である
では次に、更生保護法の「法の目的」について学習していきましょう!
選択肢の「2」と「3」に注目してください。
2.更生保護制度は、刑事政策における施設内処遇を担っている。
3.更生保護の目的は、犯罪及び非行を行うおそれのあるものに対して適切な予防活動を行うことにより犯罪を防ぎ、またはその非行性をなくし、自立と改善更生を助けることである。
「2」と「3」の選択肢は、どちらも不正解です。
では、一体何が間違っているのでしょうか。
注目すべきなのは、更生保護法の「法の目的」です。
更生保護法の法の目的には、次のような記載があります。
更生保護の目的は、犯罪をした者及び非行のある少年に対して、社会内において適切な処遇を行うことにより、再犯を防ぎまたはその非行をなくし、自立と改善更生を助けることである。
注目すべきなのは、「①犯罪をした者」「②非行のある少年」「③社会内において適切な処遇を行う」という3箇所です。
つまり、更生保護法では、「犯罪及び非行を行うおそれのあるもの」ではなく、「犯罪をした者及び非行のある少年に対して行う」のが正しい解釈です。また、更生保護制度では、「施設内処遇」ではなく、「社会内処遇」を行います。これが、更生保護制度の大きな特徴です。


3限目:【解説】社会内処遇とは何か?


一般的に、私たちは、犯罪をした人、非行のある人は、少年院や刑務所などの施設内で処遇を受けるイメージがあるかと思います。これを「施設内処遇」と呼びます。
一方で、社会内処遇は、その施設内処遇を行わない処遇のことを指します。
もう少し、わかりやすく解説しましょう。社会内処遇においては、犯罪をした人、非行のある人を「社会の中で生活させる」のが大前提になります。
そのため、彼らは、自宅から学校や仕事に通い、保護観察所の指導を受け、定期的に保護司と呼ばれる人と面会を実施します。また、その際には、生活状況を報告し、親の監督のもとで社会生活を送りながら、立ち直りを図っていきます。
保護司とは
犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアを指します。


4限目:更生保護制度に関する事務を行う3つの機関
さて、ここでは、そんな更生保護制度に関する事務を行う機関について見ていきましょう。
選択肢の「4」に注目してください。
4.更生保護に関する事務は、家庭裁判所が行なっている。
この選択肢は、不正解です。
では、何が違うのでしょうか?ここで初めて出てくる言葉になりますが、更生保護に関する事務を行うのは、以下の3つの機関です。
①法務省に置かれる中央更生保護審査会
②法務省の地方支分部局である地方更生保護委員会
③法務省の地方支分部局である保護観察所
*中央更生保護審査会とは
恩赦の実施に関する法務大臣への申出、仮釈放の審査などを行います。
*地方更生保護委員会とは
刑事施設からの仮釈放の許可、仮釈放の取消、少年院からの仮退院の許可に関する事務を行います。
*保護観察所とは
犯罪、非行を行い、家庭裁判所から保護観察の決定が出た少年、刑務所や少年院から仮釈放になった者、保護観察付の刑の執行猶予となった者に対して保護観察を行います。


☑家庭裁判所について詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。
👉参考:【知っておきたい】裁判所の5つの種類について徹底解説

5限目:更生保護の6つの対象者
さて最後に、更生保護の対象者について見ていきましょう。
選択肢の「5」に注目してください。
5.更生保護の対象者は、保護観察に付されているものに限らない。
この選択肢は、正解です。
では、更生保護にはどのような内容が盛り込まれているのかを確認しておきましょう。
更生保護には、以下の6つの内容が盛り込まれています。
①仮釈放
②保護観察
③更生緊急保護
④恩赦
⑤犯罪予防活動
⑥被害者に対する支援施策

特に、「犯罪被害を受けた方々への支援施策」も盛り込まれているのは注目です。

まとめ
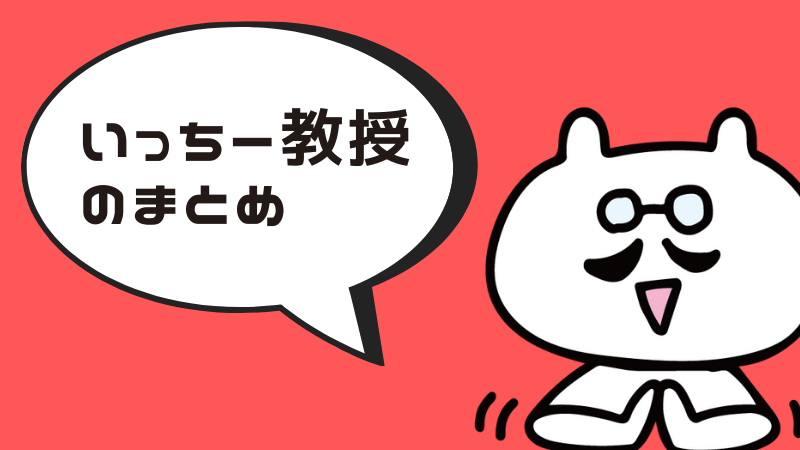
最後に、今回のテーマである「【一から学ぼう】更生保護制度についてわかりやすく解説」のおさらいをしましょう!
1.更生保護制度を基礎付けるのは、「更生保護法」である。
2.更生保護制度では、社会内処遇を行う。
3.更生保護の目的は、犯罪をした者及び非行のある少年に対して、社会内において適切な処遇を行うことにより、再犯を防ぎまたはその非行をなくし、自立と改善更生を助けることである。
4.更生保護に関する事務は、中央更生保護委員会、地方更生保護委員会、保護観察所が行なっている。
5.更生保護の対象者は保護観察に付されているものに限らない。

特に今回のテーマでは、更生保護制度の基本となる事柄について学習しました!

福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。
「参考書や問題集を解いただけではわからない…。」という方は、今後も参考にしてください!
今回の授業は、以上です!



コメント
[…] […]
[…] […]